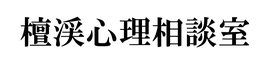日本のユング心理学では「自由で保護された空間」という言葉がよく使われます。この「自由で保護された空間」という言葉はドラ・カルフ(D.Kalff)女史が使ったもので、箱庭表現が四角い砂箱のなかで行われ、砂箱の四角い木枠が表現される箱庭の世界を区切り守っているように見えるところを言い表したのではないでしょうか。しかし、私にはその言葉がしっくりしません。
確かに絵も四角いキャンバスに描かれ額縁に入れられて絵になります。床の間の絵も掛軸に表具されて絵として落ち着きます。画家は自分の描いた絵をその絵に相応しい額縁や表具に収めたくて、額縁屋や表具師が絵に相応しい額縁や表具を作ってくれます。額縁は芸術作品に落ち着いた位置を与えるのです。画家にとって自由で保護された空間というのはアトリエで、額縁ではありません。
箱庭療法の場合、砂箱の木枠が心の自由と安全を保障するかと聞かれると、それは何かウソっぽいのです。箱庭療法を実施する場合、治療者がその場に立ち会うことが重要だと河合隼雄は言っています。そこで「横に立ってじっと見ているのですか、何か話しかけても良いのですか」という質問も出てきます。立ち会い方をどうするかは大問題です。
若い女性に箱庭を作っているところを見ないでくださいと言われた大住誠先生は、箱庭製作中後ろ向きに座って瞑想しています。後ろ向きに座って瞑想しているから心の自由と安全を保障することになるのです。箱庭を作っているところは原則的に見ないほうが良いのではないでしょうか。
砂箱をプレイルームと考えると、クライアントと一緒に作る気持ちで見ていると作る方も気が楽かもしれません。遊戯療法では治療者と子どもは一緒に遊ぶので見られている感じはないのですが、箱庭制作では治療者は側に立っているので見る側になりがちです。見られると作る人にとっては安全な空間ではなくなります。
元々字を書いたり絵を描いたりするところを見られたら嫌です。私は幼いとき戦争ごっこの擬音を発しながら飛行機の絵を描いていました。そこにやってきた近所のおじさんが覗き込んで上手だねと言ったとたん、私の絵を描く意欲はいっぺんに無くなってしまいました。それは凄い外傷体験になって、以後絵が描けなくなってしまいました。
何かしているところを見られるのは誰でも脅威です。釣りをしている人でもそうではないでしょうか。書痙という神経症があります。この言葉は広辞苑にも載っていて古くからあったことがわかります。人前で字を書くと手が震えて、時にはペンが飛んでしまいます。ある車のセールスマンはお客さんの前で書類を書けず、ちょっとすみませんと外へ出て書いて戻ってきて説明しなければならないと悩みを訴えました。
ですから何かを一緒にするときは別ですが、相手にだけ表現させるときは見ない方がいいと思います。大住誠先生のように後ろ向きに座る必要はなく、見なければいいのです。箱庭ができあがったら見せてもらう、それでいいのです。砂箱は絵で言えば額縁付きのキャンバスです。砂箱の枠は心の自由や安全とは関係ないと思います。まして、バウムテストを描かせるとき、黒枠を付けて描かせるなんて、あなたの遺影を描いてくださいというような感じで、私には到底出来ません。
それでは心の自由と安全はどうしたら保障されるのでしょうか。
そのためには話を聞く人、つまり治療者が本当に真剣で真面目で誠実に、相手の血の噴き出る、時には膿の溜まった傷口をまともに見て手当をする態度が必要です。小倉清先生の八十歳の記念文集『時の流れ』に書かれた自伝には、歯科医のお父さんが患者の少女の口の中の腫れ上がったところをメスでついたら、そこに溜まっていた膿が飛び出して見ていた自分の顔にかかったと書いてありました。これと同じようなことが心の悩みを聞くカウンセリングの現場には常に生じています。
真面目に真剣に誠実に向かい合うとき相手は本当の真実の悩みを打ち明けてきます。それは本当のことを話す親友の関係に似ています。河合隼雄は親友の説明で次のようにどこかに書いています。「深夜に友達がやってきて、実はトランクに死体が入っているのだけどどうしたら良いだろう」という相談を持ちかけられるような関係であると書いています。親友同士の本当の話で、心の安全が保障され、世界への視野が広がるのです。
人は真剣に誠実に心の真実を話し合うとき、そこに平安と自由が広がるのを経験します。そのために私たち心の専門家はあるのです。ですからカウンセラーは常に自分の心の真実に深く向き合う用意をしていなければなりません。教育分析の必要性がここにあるのです。
村上春樹は短編集『女のいない男たち』の「イエスタデイ」中で次のように書いています。
“「あのな、中学校の終わり頃から、おれはセラピストのところに定期的に通ってたんや、親とか教師とかに、行け言われてな。学校でその手の問題をちょくちょく起こしていたわけや。つまり普通やないということでな。セラピーに通って、それで何かがましになったかというと、そういう感じはぜんぜんない。セラピストなんて、名前だけは偉そうやけど、ええ加減なやつらやで。わかったような顔して、人の話をうんうん言うて聞いてるだけでええんやったら、そんなもんおれにかてできるわ。」
「今でもセラピー通ってる?」
「ああ、今は月二回くらい通てる。まったく金をどぶに捨ててるようなもんやけどな。えりかはセラピーのことはお前にいわんかったか?」
僕は首を振った。
「自分の考え方がどこが普通やないのか、正直言うておれにはようわからんのや。おれの見方からしたら、おれはあくまで普通のことを普通にやっているだけやねん。そやけどみんなは、おれのやっている大方が普通やないと言いよる」
「たしかにあまり普通とは言えないところもあると思う」と僕は言った。
「たとえばどんなとこが?」
「たとえばおまえの関西弁は、東京人が後天的に学習したにしては、異様なくらい完璧すぎる」
木樽はそれについては僕の言い分を認めた。“
村上春樹にとって河合隼雄先生はただ一人の理解者で、しかもセラピストですから、セラピスピーのことを完全に否定してはいませんが、話をウンウン言って聞くだけなら俺にだって出来る、金をどぶに捨てるようなものだと酷評しています。
その後、小説では二人の真剣な対話になります。どんなところが普通でないかと問われ、お前のおかしいところは、東京育ちのお前が完璧な関西弁をしゃべるところだと問題点をはっきりと指摘して、正面から真剣に対話します。このような真剣に正面から向き合い対話をするとき、そこに本当の心の安全と自由の境地が開かれて行くのがこの記述からわかります。本来の自分のいち面である東京弁を捨てて関西弁にしているのは何のためか、それは小説の主題ではないから深められていません。小説の主題はあくまで幼馴染の男女、木樽とえりかの関係の行く末だったのです。
この真剣な対話的な面接をカウンセラー側がすると、クライエント側も自分の問題に直面しなければカウンセリングは続きません。何度か面接したあるクライアントは不眠が酷くなって心療内科で眠剤をもらいますから、カウンセリングはしばらくお休みにしますとメールしてきました。その時この人のたましいは「眠らないで、目を開けなさい」と身体言語で呼びかけていると思いましたが、その人の意識は眠りたい、目を開けたくないと考えているので、時が来るまで待つことにしまた。“目を覚ませと呼ぶ声が聞こえ”るまで。
これまで真剣な対話的面接をしてきた相談を振り返ると、共感と受容だけよりは遥かにクライアントが意欲的になって面接が継続するようになりました。真剣な対話的面接は効果的ですから試みてください。うんうんと話を聞くだけよりも遥かに有意義な面接が出来ます。