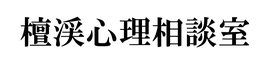(このエッセイは臨床心理士向けのものです)
カウンセリングが宗教と違うところは、自分を導いてくれる人に対して文句を言えるところである。文句をつけられることはめったにないけれど、時に出てくる。
しかし、その大部分は無意識に行われる。神経科のクリニックを受診しながら、他のカウンセラーのところに行くのもその一例である。自分の心理状態の短い報告とそれに基づいた投薬では不満な人が多く、じっくりと話を聞いてもらうためにカウンセラーのところに来られる。
カウンセラーに面接を受けていても整体や催眠やその他の民間療法に通われる人は少なくない。
カウンセラーはそのような事態を、クライアントが自分の内面にしっかりと向き合えないと見ていることもある。
しかし、これをもう一方から見ると、カウンセラーの資質に欠けているところがあるから他のところの面接も並行して受けるのである。しばらく他所へ行ってまた帰ってくることもある。
ある事例報告で、最後にクライアントが、先生の面接は物足りなかったから他のところに行っていたと言っていた。治療者はその点について、自分もその間自らの研修を深めていたので、内面を深めるという共時的な現象が起こっていたのだと説明していた。共時的な現象が生じていたと説明すると立派に聞こえるが、要するにクライアントから見たら治療者に何かが足りなかったのであり、その何かは不明なままである。クライアントが外で求めたものと治療者が内面を深めて得たものとの関係がはっきりしない。
他のある事例報告では、それは極端な体重減少を起こす困難な事例で、10数年の間に何回も入退院を繰り返していた。その事例は長い経過の後にやっと祖母も含めた家族環境について具体的に不満を述べ始めてから良くなっていた。
この事例を最後まで読んだとき、もし治療者が、クライアントが育った家族環境の分析についてもっと積極的にかかわっていたらどうなっていたのだろうと思った。10数年もの間死に瀕するような体重減少を起こしながら回復してはカウンセラーのところに帰って行く関係は素晴らしいけれど、ひどい体重減少の反復と入退院に費やしたエネルギーとやせ症からの回復の過程が私の中で何かつながらなかった。
治療者は精神分析的スーパービジョンを受けているので当然家族環境も視野に入れているはずである。けれども何か治療者の方に家族関係について踏み込む力が足りなかったのではないかと考えてみた。知的に考えることとかかわることは別である。そこが心理療法の実際の難しいところである。机上で心理療法を考える物書きの心理療法家と心理療法の実際家の違いがそこにある。
一般的に治療者は、治療的理論に添って面接の構造を守り、関わって行けばそれ以上のことはしてはいけないと考えているのではないか。それに対してクライアントの方はもっと人間的なかかわりを求めていることがある。時として、人間的なかかわりは新興宗教的民間療法の方がはるかに力を持っている。臨床心理士が治療的枠組みにとらわれ、人間的なかかわりを忘れていると、クライアントはもう一つ踏み込んだかかわりを求めて他のところへ行く。治療関係が緩み、ついにはクライアントに見放されてしまう。
命にかかわる体重減少は、事態が心理療法の限界を超えていることを示しているけれど、それを逆に見れば、治療者がクライアントのたましいのいのちにかかわる重大な見落としをしているとの警告であるかもしれないのだ。
極端な体重減少で、心理療法の限界を超えたとき、医療の援助が必要で、医師と臨床心理士の協力がしなければならない。そのチームワークでクライアントが良くなっていくのだが、その時、治療者に何かが足りないから、他領域の協力が必要なのではないかと反省してみる必要があるのではなかろうか。そこにスーパービジョンの本当の必要性が出てくる。
以上のようなことを以前から考えていたが、なかなか言い出せなかった。しかし、ある事例に接して、やはりこの点について書き残しておく必要を感じたので以下にもう一つ述べておく。
ある遊戯療法の事例で、子どもがわざとものを壊したり、玩具を隠して持ち出したりを執拗に繰り返していた。明らかに子どもは治療者を怒らせ、叱責してもらいたいがための行動を繰り返していた。それに対して治療者は決して叱らないことを原則としていた。常に愛情をもってかかわり、子どものひねくれた愛情欲求を素直にしようと治療者は頑張っていた。その態度は治療者と常に一太刀交わして、対等な人間関係を築きたい子どもの気持ちと矛盾したかかわりになっていた。
その事例で興味を引いたのは、長い経過の中で少し年上の子どもにお前はそんなことをしているのかと叱られたとき子どもの問題行動がちょっと収まったことである。ついには学校でクラスメイトのものを黙って取って、担任の先生にひどく反省させられ、その後しばらくしてプレイルームからの玩具の持ち出しが治まって行ったことである。これで子どもの治療場面での問題行動はほぼなくなったように治療者も感じていた。
この事例では治療者が叱責しなかったから年上の子や担任が叱る役目を負わされたのではないか、もし治療者が温かい愛情と共に叱ることもできるバランスのとれた人格を持っていたなら先輩や先生に叱られることがなくて済んだのではないか、長い治療経過の中で子どもは繰り返し治療者を怒らせるような嫌がらせをしていたが、それをしなくて済んだのではないか、意地悪を続けたことは却って子どもの心の傷にならないかという気がかりが心に残る。
翻って考えてみると、問題を起こして先輩や先生に叱られ、それで心のつながりができるのなら将来的にはその方が良いではないかと思える。
執拗に繰り返される入退院、あるいは治療者に対する嫌がらせ、この人に話しても得られるものがないという物足りなさ、そういうクライアントの不満は独立して面接している私には思い当たることが多く、自戒しなければならないところである。
河合隼雄先生の先生、マイヤー先生はずっと分析を受けるているので、なぜそんなに個人分析が必要なのかと聞いたら、俺の足りないところはいっぱいあると答えられたという。
このような治療者の力の不足を云々することができるところが、心理療法が新興宗教と異なるところである。治療者はこの点を教育分析で分析し補う努力をすべきではなかろうか。教育分析が必要な理由がここにある。