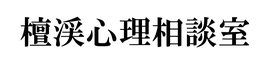村上春樹『1Q84』を読む3
―『空気さなぎ』の物語―
カウンセリング・だんけ 西村 洲衞男
小説『1Q84』は空気さなぎの発想があってできたものではないかと思う。空気さなぎがこの小説の原点だと思った。ねじまき鳥では井戸掘りだったが、ここでは空気の糸を紡いでまゆを作り、たましいを包むことができるようになっているところがすばらしい。幼虫は自ら糸をはきだしてまゆを作り、その中でさなぎとなり、さなぎの殻がときがくると割れて成虫が出てくる。成虫はまゆを破って外界に出てくる。空気さなぎは見た目はまゆだで、割れて中身が見えるというところからまゆでなくさなぎでなくてはならない。
小説『空気さなぎ』の著者、ふかえりこと深田絵里子は読字書字障害で本を読むことも字を書くことも苦手である。そのふかえりが小説を書いたのは二つ年下のアザミの協力があったからである。ふかえりが物語り、それをアザミが文章にし、タイプし印刷して出来上がった小説が『空気さなぎ』である。アイデアはとても良いが文章が稚拙であるため出版社の編集者はまだ小説家として世に出ていない天吾にゴーストライターを依頼する。その小説の全容はBook2の最後の方で明らかにされる。物語は次のようである。
小説は「集まり」に所属する10歳の少女の物語である。少女は「集まり」で山羊の世話を任されていた。その中の一匹の山羊は老齢で、彼女が疲れて世話をし忘れた夜に死んだ。山羊が死んだその罰として死んだ山羊と共に暗い蔵の中に閉じ込められた。夜になって死んだ山羊の中からリトル・ピープルが出てくるのを少女は見た。そのリトル・ピープルはふかえりの心を読み取って話をすることができた。心の中で思うとそれは言わなくてもリトル・ピープルに通じ、互いに話をすることができた。
死んだ山羊という通路を通って蔵の中にでてくることができたリトル・ピープルは、空気さなぎを作って遊ばないかという。空気の中から糸を取りだしてそれですみかをを作っていくのだ。それはだれのすみかかと聞くとそのうちにわかるという。
少女が蔵に閉じ込められていた期間内には出来上がらなかったが、好奇心に駆られてしばらくして見に行くとそれはさらに大きくなっていて、さなぎは割れ始めていた。その隙間から覗くと、裸になって仰向けになり目をつぶっている自分がいた。リトル・ピープルは眠っているのはドウタでキミはマザで、ドウタはマザの心の影だという。少女は少女に違いないが、マザとドウタにわかれている。ドウタはパシヴァ、つまり、知覚するもので、知覚したものをレシヴァに伝えるのだ。パシヴァであるドウタはリトル・ピープルが住んでいるところとここを結ぶ通路となり、そのためには生きている必要があるという。つまり、眠っているドウタが目覚めると、ドウタを通じてリトル・ピープルはこの世に出てくることができるのだ。ドウタは時間がくると目覚め、目覚めると月が二つになるという。マザの影であるドウタがいなくなるとマザはどうなるかと聞くとリトル・ピープルはそれには答えなかった。
ドウタという自分の身代わりができた少女は「集まり」を抜け出して父親の友達のところで暮らす。「集まり」には瓜二つのドウタが残っているので、周りの人は気づかないかもしれない。両親はドウタが本人でないことはわかるはずだが探してこない。少女は自分を守るためだ悟る。
少女はやがて中学生になる。学校に馴染むことができないでいると一人の重い病気を背負った男の子と仲良くなる。その男の子は休み時間に本を声を出して読み上げてくれる。少ししゃがれた声だがはっきりと聞き取れ、少女は男の子が読み上げてくれる物語にうっとりとなり、じっと耳を傾ける。
そのうちリトル・ピープルが眠っている男の子の傍に現れ空気さなぎを作り大きくしていく。さなぎは割れ、中を覗くとそこには3匹の蛇がいた。3匹の蛇は互いに絡み合いほどけなくなってぬるぬるとうごめいていた。うごめくほど苦しむ蛇たちの横で男の子は眠っていた。やがて男の子は病が重くなって療養所に送られてしまった。このことによって、自分が誰かと仲良くなっても月が二つある世界では常にこのような危険があることを悟った。
少女はやがて自分で空気さなぎを作り始める。ドウタを通じてリトル・ピープルが出てきたのだから、空気さなぎを通って逆にたどれば、マザとドウタの秘密を探り当て、失われてしまった男の子も救いだせるかも知れないと考えたのである。
少女は空気さなぎを作りながら考える。自分はマザなのかドウタなのか、私はドウタと入れ替わったのか、考えれば考えるほどわからなくなる。私が私の実体であることをどのように証明すればよいのかと戸惑ってしまった。
物語は少女が通路の扉を開けようとするところで終わっている。
月が二つ見える世界に住んでいる青豆は、すべてはこの物語からはじまって、自分はこの大小二つの月が見える世界に引き込まれてしまったのではないかと考えた。自分はこの物語のどこに当てはまるのだろうかと考える。
この物語を読んで、青豆は天吾がふかえりのアイデアによってうまく作り上げた物語の世界の中に取り込まれ生きていると感じた。「私は今、天吾君の中にいる。彼の体温に包まれ、彼の鼓動に導かれている。彼の論理と彼のルールに導かれる。そしておそらく彼の文体に、なんと素晴らしいことなんだろう。彼の中にこうして含まれているということは」。幸せいっぱいになった青豆は死ぬ覚悟ができたと感じる。
彼女は首都高速に再び乗り、はじめに降りた階段がないことを知ると拳銃を取り出して自分を撃ち死んでしまう。
今度の『1Q84』は素晴らしいと言うと、ある若い女性読者が、なぜ青豆は死んだのですか、自分は青豆に似た性格だから生きていてほしかった、生きる道はなかったのですかと聞いてきた。その質問に応える資格は私にはない。物語の発展にはいろいろな可能性がありうるのだから、それぞれの人が自分のたましいで考えたらいいと思う。青豆が当面した状況を自分の本当の問題として深めるとき、その個人の無意識の本質がその個人に向かって応えるのではないかと思う。その問いがその個人の本当の問題であれば、その人の無意識が必ず応えてくれると私は考える。これは読者一人一人の問題である。青豆は拳銃で自分の脳天を撃って死ぬが、二つの月がある世界にいる青豆は、天吾が天吾の息遣いで物語る物語の中で、天吾の文体に包まてれ幸せを感じたのだ。青豆は天吾と叫び、たましいの言葉に乗ってその世界から脱出したのだと思う。
青豆は死んであの世界から脱出し、天吾の目の前の父親のベッドの上に、天吾とたましいが叫んだことによって彼女自らが紡いだ空気さなぎの中に再生することができたと見ることができるのではなかろうか。『空気さなぎ』のおしまいに少女が空気さなぎを作って男の子の救出に向かったように、青豆も空気さなぎを作って天吾の救出に向かったのだと私は思った。見事目的を達してシステムから逃れ、青豆は天吾のたましいとなり、これからの人生を導いていくことになって物語は終わった。