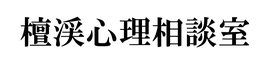世界観というと、先ずは天動説、そして地動説を思い浮かべる。天動説から地動説への変化はコペルニクス的転換と呼ばれている。主観的な見方に代って客観的な見方が出てきて、天動説は地動説になった。フロイトが無意識と言う概念を基に精神分析を始めてとき、西欧の人々にとってはコペルニクス的転換があったかもしれない。日本人の場合、無意識ということはそれほど意外なことではない。日本人にとって無意識と言うことは当たり前ではないか。むしろそれを考えていいない方がおかしいと思われるのではなかろうか。精神分析が導入されたとき、無意識ということをことさらに強調することに対して抵抗が起こったのではなかろうか。気がつかないことが当たり前とか、気づいているのに気づいていないことにしていることが日常になっているところに、わざわざ無意識という概念を当てはめて考えを進めていく心の見方、そういう精神分析は、知的な概念化を好む人々のものになったのではないかと思う。
フロイトが精神分析を打ち立てて一世紀経ってもなお私たちはフロイトが考えた心の世界観に基づいて考えている。人と人との心の関係を転移、逆転移という言葉で言い表している。転移は元々親との関係が分析家との関係に転移することを表した。それが今では心の関係一般を言い表す言葉になり、力動的な心の世界観が今なお私たちを覆っていて、そこから抜け出せないでいる。というよりも抜け出すことも考えていないのではないか。私たちは互いにフロイトの力動的な心の見方によって、心の研究の相互理解を容易にしているので、そこから抜け出せないのだ。フロイトの考え方は、今世界の共通語になりつつある英語のようなものか、それともみんなが共通に信じていた天動説のようなものではないのか。私たち、心を客観的に研究するものたちはこのことをしっかりと考える必要があると思う。
最近、スクール・カウンセリングの心理学にとって何が大切かを考えたとき、「客観性」ということに思い至った。
フロイトの心理学やユング心理学を振りかざしても、教育現場の先生方には通じない。それは通訳の要る外国語のようなものだ。私たちは先生方と話すのに当たり前の言語が必要なのだ。共通の言葉で目の前の現象を記述し、相手にわからせる必要がある。
人柄を判断すること、困った人を援助することは臨床心理士でなくてもできる。人々が余りしないことで臨床心理士がすること、それはクライエントを中心にして、心の現象を観察・記録し、それをかかわりのある人に示して、心の問題はどのように現象しているのか、何が大切か、何ができるかを客観的に考えていけるところにわれわれの役目があるのではなかろうか。
その科学を信奉する人の見方は、科学者という権威者の見方に頼っていて、その信じ方は天動説に対するのと大して違いはないのではないか。しかし、科学を信用しないで自分を信じて生きている人は、一人一人が個性的な世界観を持って生きているのではないかと思い始めた。私たちが住むこの世界で何を経験し、その経験に基づいて考えると世界はどのように見えるのか、これまで世界をどのように見てきたかということが重要と考えられる。それで自分を支えて生きようとしている。
客観的に見ると言うと、自分以外のところに視点の中心があるような気がするが、実際は大体自分に視点の中心をおいてものごとを見ているのである。特に、中年以降の、経験を積んで自信を持った男性は自分の常識を世界に通用すると思っている人が少なくない。それはともすると独善に至りやすい。私もその一人であるか気をつけなければならないが。
客観的という場合、自分の見方と同時に、人はどのような見方をするかを考慮し、誰にでも明らかなような見方をしたとき、私たちは客観的というのではなかろうか。だから、共通主観的といった方が実際は適切かも知れないのである。共通主観的に見た世界観、それは一体どのようなものであろう。新聞やテレビのニュースを見て作り上げる世界観は大体同じようになるであろう。一方、個人の生活経験を元にした世界観は、一人一人みんな異なってくるのではないか。私たちカウンセラーはそのように一人一人異なった世界観のだ下に仕事をしていると思う。その中にあって、自分の客観性を保つには、多くの人と話し合い、わかりあっていく必要がある。
話し合いの中で、理解を深めていくために、われわれ臨床心理士は生徒や親、そして先生とカウンセラーを含めた人々の動きを事実に基づいて描き出して、それをみんなで検討できるようにすることではなかろうか。そのような観察事実に基づいて考えること、それを日本語で体験と思索というが、英語に直すと、evidence
basedというのではないか。最近の心理療法にエビデンス・ベイスド・セラピーと呼ばれるものがある。それはそういうものではないか。様々な心理療法の理論に飽き足らなくなった人々が行き着いたところがここではないかと思う。
フロイトやユングという開拓者もそうであったが、自分の経験から考えて自分の学問を開いて行ったのだ。そういう人は大勢いるが、有名にならなかった人はただスター性がかけていたのかもしれない。例え有名でなくても、体験と思索から生まれたものはいつも参考になる。それはいつも、これまでの考え方は果たして正しいのかと、疑問を投げかけながら学んでいるということにつながる。そこに発見の喜びがある。
最近、臨床心理士はどうですかと女子学生から聞かれる。臨床心理士も限界が見えてきたと思われる。そこで私は、臨床心理士はいつまでもパートの仕事だが、いつも勉強しているととてもやりがいのある仕事ですと答えている。勉強して自分の視野を広め、客観性を高めていく仕事なのである。それが幸せをもたらすかどうかはわからないけれど。というのは、いつもユニークな考え方になるから、多少とも理解される度合いは少ないことを覚悟しなければならないからである。