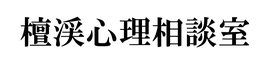少し前に易(えき)について書いた。易に関しては、河合隼雄先生が印象的なできごとを「宗教と科学の接点」(岩波書店)の中で紹介している。スイスのユング研究所でユング派の分析者としての資格を取るために訓練をしていた時のエピソードだ。
ユング研究所では研修が進むと実際にクライエント(相談者)をとって分析をし、指導を受けるようになる。河合先生はご自分がアジア出身者(今から60年以上前でおそらくヨーロッパ圏在住のアジア人も珍しかったに違いない)で語学力も十分ではないのにクライエントが来るのかと心配されたそうだが、やってみるとすぐにクライエントは集まったという。しかしある時、思わぬ条件が重なって、クライエントが立て続けに離れていった。資格を取るには規定の時間の分析経験を積まないといけない。これでは資格が取れないと落ち込み、易をたててみた。その結果を分析家のひとりであるフレイ先生に話しをしたところ、フレイ先生も自分も易をたててみると言い出したという。
易は同じことを2度占うことを禁じている。河合先生は強く反対したが、フレイ先生は、自分が関わることで状況が変わるのだから同じことを占うことにはならないと主張し、2人の間でかなりの議論となったそうだ。結局はフレイ先生も易を試みたのだが、そこで出た卦はなんと河合先生とまったく同じものだったのである。
その後、河合先生は易の結果も踏まえてまずは自分の分析に集中することが大事だと考え、事情を話して、クライエントの分析を一時中断したのだという。十分よしと思えたところでクライエントの分析を再開したが、クライエントは最初に離れていった人も含めて戻ってきてくれたのだそうだ。
同じ卦が出たというドラマチックな展開(卦は全部で64通りあり、同じものが続けて出る確率は単純に考えても64×64分の1である)でとても印象的だったのだが、その割には、このエピソードに関して肝心なところでいくつか思い違いをしていたことが最近分かった。
まず、私はこの話を河合先生とフレイ先生の間のことではなく、もうひとりの河合先生の分析家であるマイヤー先生との間の出来事で、しかも、易をたてたのは河合先生がユング研究所での資格試験の時のことだと思っていたのだ。
河合先生がユング研究所での研修の最後、ユング派分析家の資格を得るための試験の面接をきっかけに体験したできごとは、かなり有名なエピソードだと思う。面接の時の質問に対する河合先生の返答から、面接官のひとりの分析家と対立が生じ、資格を得られるかどうか分からないという状況にまで陥ったのだそうだ。試験を合格とするのか資格を授けるかどうかで研究所内の大激論ともなり、途中、遠い日本からわざわざここまで来ていることを考慮してお情けで資格を授けようという話も出たが、河合先生はそんなことなら資格はいらないと啖呵を切ってしまう。しかし後から相当な犠牲を払ってスイスにまで来たのにと落ち込んで…という経過があり、更にすったもんだの末に資格を得るという、ドラマチックな展開となる。詳細は「河合隼雄自伝 未来への記憶」(新潮文庫)に詳しいので、是非読んでください。ユング研究所での体験がいろいろと語られていて、前述の易の話も出てきます。
私はてっきりこの試験のところで易をたてられたと思っていたのだが、全くの思い違いだった。自分がどうして思い違いをしたのか改めて考えてみると、両方とも河合先生にとっては一種、危機的な状況であったこと、しかもユング研究所でのドラマチックなエピソードであること、が共通していたからだろう。フレイ先生をマイヤー先生に置き換えたのは、河合先生がマイヤー先生について書かれたものや、河合先生が監訳を務められたマイヤー先生の本も読んでいたこともあって、河合先生、ユング研究所と言えばマイヤー先生、という思い込みがかなり強かったからかもしれない。2人の先生の関係性に強い印象を受けていて、一種の憧れや尊敬の念を抱いていたからであろう。
それにしてもクライエントが離れていった時に、河合先生がクライエントの分析を一時中断されたのもすごい決断だと思う。無意識の流れを真に尊重する態度がないとできないことではないだろうか。こういう真剣で真摯な態度があったからこそ、資格試験の時のような面接官との間で激論を生じ (河合先生はケンカに近かったと話されている)、更には研究所全体を巻き込むような激論をひきおこすことになったのだと思う。河合先生のパワーを感じるエピソードだ。
こういうことを知ると、やはり河合先生はすごい人だったのだなぁと思う。尊敬の念は強いが、当然、私は河合先生にはなれない。河合先生になる必要もないと思っている。私は私になるしかなく、私は私でやるしかない。ただ、自分なりに真剣に、真摯に、無意識の流れを尊重していきたいと思う。