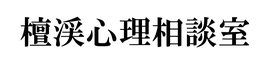勉強会や研究会などは定期的に積極的に参加している。この仕事は経験も重要だが、しかし経験だけでもできない。知識やセンスなども大事で、それを養うためには日ごろの勉強が大切だ。
ただ勉強会や研究会などで知識をつけることが大事かというと、どうもそれともちょっと違う気がする。話を聞いてすぐに活かせるような実用的な知識がものを言う仕事でもないだろう。学ぼうとすること、勉強会などに積極的に参加しようとすること、その姿勢が大事だということなのかもしれない。
カウンセリングに来る人それぞれに悩みは異なり、置かれている状況も、その人の性格や考え方もみな異なる。こちらが話を聞いてすぐにこうしたらいいとアドバイスでき、それで解決できることなどほとんどない。すぐに解決できるような悩み、答えが出せるような問題ではないからこそのカウンセリングなのだ。ではカウンセリングでは何をするのかと言えば、いろいろあるけれど突き詰めて言えば「良い関係を作ること」、それがとても大事なことだと考えている。
カウンセリングにおける「良い」関係というのは、いわゆる世間一般で言う良い関係というのとは少し異なる。カウンセリングにおける関わりは、家族や友人との関りとは別で、そういった人たちとの「良い」関係の中では言わないようなこと、例えば気を使ってぐっと我慢するようなこと、言ったらいけないと感じることも素直に、積極的に、率直に話すような関係だ。こういう関係をもとにして、相談に来られた方は新しい何かを見出していくのだと考えている。大切なのは、カウンセラーが新しい何かを差し出すのではなく(差し出せるものでもない)、何かを見出せるような土壌を協力して作っていくことで、野菜作りに例えるなら、カウンセリングは作った野菜をカウンセラーが用意して相手に渡すところではなく、良い野菜が収穫できるような土を作ることを一緒に考えるようなところだと言えるだろう。
河合隼雄先生は、しばしば「何もしないことに全力をかける」と言っていたが、本当に何もしないわけではなく、全力をかけて何かをしておられたからこそ、「何もしないことに全力をかける」という言い方になったのだと思う。今ある土をもとにして良い土を作っていくためにはそれなりに時間が必要で、小手先の工夫や対応ではただのその場しのぎにしかならない。相談に来られる方の前に座って話を聞いていると、「何もしないことに全力をかける」というのはどういうことなのか、何もしないためには何をすればいいのかと考えることがある。普段から勉強会や研究会に参加するのも「何もしない」ために必要なことだ。しかしそれだけではない。自分自身が日々の生活のなかでこころを大事にして生きることも重要なことだと考えている。