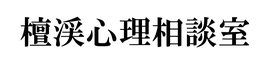週に一度エッセイを書いてホームページにアップすることを続けている。心理相談室は積極的に宣伝するようなところではないと思っているが、全くアピールしなければ誰にも知られず、来てくれる人もいなくなる。そうなれば相談室を維持することすら難しい。そこでホームページをこの相談室の宣伝の場と考えて、積極的にエッセイを書くことにした。
少し前のことだが、前田重治先生が亡くなられたと聞いた。前田先生は日本に精神分析を紹介し広めた古沢平作先生の分析を受け、ご自身も精神分析の分野で活躍された方だ。この相談室の前室長の西村洲衞男先生は前田先生との交流もあったようで、ずいぶん昔のことだが、ある本と一緒に送られた前田先生からの手紙を見せてもらったことがある。
確か前田先生の書かれた「図説 臨床精神分析学」のあとがきのところだったと思う。今、手元にこの本がないので正確な言い回しとは異なるだろうが、ある有能な心理士に「この本を書かれている間は臨床の腕が落ちたのではないですか?」と聞かれ、どきっとした、というようなことが書いてある。臨床場面で実際に起こることや無意識の心の動きを図で表わして説明するとなると、かなり割り切った考え方をしなければならなくなる、そういう本を書いている時は実際の仕事に影響が出ることもあったのではないか、という問いかけだが、あとがきにそれをわざわざ書かれたということは、前田先生もかなり核心を突かれたような感じがされたのだろう。
見せていただいた手紙には、この質問の主が西村先生であることが書かれていて、その事実を知ってびっくりしたのだが、それ以上に、西村先生らしい問いかけだなと思ったのをよく覚えている。西村先生は人をドキッとさせるような、核心を突くことをしばしば言われた。
大学時代、私はたった半期だけだが、前田先生の授業を聴く機会があった。カウンセリングの仕事がしたいという熱意と決意だけは持って大学に入学したのだが、実際は臨床心理学という学問のことは何も知らず、実は河合隼雄先生の名前すら大学に入ってからはじめて知ったというぐらいで、同級生の中には前田重治先生がいるからこの大学に来たという友人もいたのに、私は前田先生がどんなにすごい先生かよく分かっていなかったと思う。せっかく前田先生の授業を受講したのに、その講義で覚えていることといえば、相談室の宣伝についてという、前田先生の専門の精神分析とはかけ離れた、雑談のような話だけなのだ。
当時はまだ臨床心理士の資格がなく、開業の心理相談室などほとんどなかった時代だった。ただ私の在籍していた大学では一般の人に向けた心理相談室があり、大学の先生方や大学院生が相談業務を行っていて、それなりの利用はあったようだ。前田先生が講義の合間にふと思いつかれたように話をされたのはその相談室のことで、派手な宣伝をするのもどうかと思うが、なにもしないでいると人は来ない、「来る人が少なくなってきたなと思った頃に、新聞に広告を載せるんだよ」と話されていたのを、どういう訳だかよく覚えている。目立たない小さな広告だが、やはりそれを見てくる人がいたそうだ。
なぜ講義の本筋とは関係のない、こんな話を覚えているのかよく分からないが、穏やかで誠実そうな前田先生のイメージと、「広告」という商売に関する言葉がうまく結びつかないところがあったのかもしれない。あるいは、ただただカウンセラーになりたいという思いだけ強く、どうやって生活していくかという、具体的・現実的なことを全く考えていなかった学生の私には、心理相談室を宣伝する必要性など考えてみなかったことであり、それが前田先生の口から語られて驚いたのかもしれない。
それにしても、前田先生の授業に出席しておきながら、こういう話しか覚えていないのはつくづく残念で情けないことである。よく考えてみれば、私が出席した授業は、前田先生が退官前に行った最後の講義であって、力が入った充実した講義だったのではないだろうか。前田先生が専門分野のことについて語られたことをもう少し覚えていればなぁとは思うが、当時の私には先生の話を吸収する力がなかったのだから仕方がない。
改めて考えてみると、この相談室のアピールの仕方、積極的に宣伝はしないが、ホームページにエッセイを書くぐらいのアピールはする、というやり方は、前田先生のやり方を取り入れているところがあると言えなくもない。当時の私に専門分野のことについて理解する力はなかったが、現実的なところにどう対処するかについてひとつの知恵を授けてもらったのかもしれない。