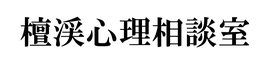長谷川泰子
夏目漱石の「永日小品」という随筆集の中に「猫の墓」というタイトルの文章がある。
「猫の墓」は、例の「我輩は猫である」のモデルになった猫の最後の様子を描いたもので、解説によれば、漱石はこの猫の死後、何人かの知人に「…うらの物置のヘッツイの上にて逝去致候埋葬の義は車屋をたのみ箱詰めにて裏の庭先にて執行し候。但主人『三四郎』執筆中につき御会葬には及び不申候…」というような通知を出しているのだそうだ。“埋葬の義”はそれなりに丁寧に行われたようで、エッセイの中ではその時の様子が記されている。鏡子夫人が墓標を買ってきて、漱石に「何か書いてやってくださいと言う。自分は表に猫の墓と書いて、裏にこの下に稲妻の起こる宵あらんと認めた」とあり、この墓標の下に猫を埋葬したようだ。最後は「猫の命日には、妻がきっと一切れの鮭と、鰹節を掛けた一杯の飯を墓の前に供える。今でも忘れたことはない。ただこのごろでは、庭まで持って出ずに、たいていは茶の間の箪笥の上へ載せておくようである」という文章で締めくくられている。
漱石の妻が悪妻だという説は昔から根強くあるようだ。しかし「猫の墓」のような文章に出てくる夫人の様子を見ると、本当にそうなのかと疑う気持ちも出てくる。別の漱石のエッセイでは妻の観劇に仕方なしに付き合うような話もあったように記憶しており、漱石にしてみれば面倒なことをやらされたこともあっただろう。漱石を敬愛し尊敬する周囲の人々、例えば弟子たち、にしてみれば、大作家・夏目漱石の妻に望むものも多かったのではないか。現実の妻である鏡子夫人に対する反感や幻滅を持ちやすく、そういったところから“悪妻説”も出てきたのではないかとも考えるが、どうなのだろう。
例えば鏡子夫人の語りをまとめた「漱石の思い出」のような本を読むと、漱石が妻にずいぶん荒い態度で接していたことが分かる。鏡子夫人が漱石の熊本時代に入水自殺を図り、未遂に終わったこともよく知られている事実だ。「猫の墓」のような文章から想像する関係性とは違う、緊迫した夫婦関係もあったのかもしれない。本当のところは分からない。見る側・判断する側の立場、気質やパーソナリティー、相手に対してもともと持っていた印象など、様々な要素によって、相手の何に注目しどう判断するかは大きく変わってしまう。何を良しとして何を悪とするかの判断基準も人それぞれだ。Aさんが見ているXさん、Bさんが見ているXさんは、同じようでいて別ものであり、そのどれもがおそらく実際のXさんとは異なっているものだろう。
だからといって、Aさんが見ているXさんとBさんが見ているXさんは、一種の幻で、実際のXさんとは全く違うものかというと、そうとも言えないと思う。AさんBさんにXさんがそう見えることは本当のことであり、事実間違いのないことだ。Aさん、Bさんの真実の思いがそこにある。漱石が描いた鏡子夫人もひとつの真実であり、ある人には鏡子夫人が悪妻に見えたことも本当のことなのだ。
こういうことを臨床心理学的には「心的現実」という言葉で扱う。私たち臨床心理士は、こういったたくさんの矛盾に向き合う。矛盾する様々な事実をどれもみな大切に扱う。矛盾があるとも思うし、矛盾ではないとも思う。矛盾しているからといって排除することもない。臨床心理士には相反するたくさんのものに向き合う自我の強さが求められていると思う。