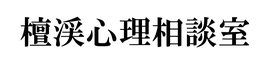長谷川泰子
青年期の始めごろだろうか、精神的に自立してくると、自分の親を一人の人間として見られるようになってくる時がある。そうすると完全にとはいかないまでも、親の長所・短所も少し距離を置いて冷静に語ることができるようになってくる。親の失敗なども、仕方ないと許容できるところが出てくる。
そうなるまでは、どこか父親・母親を、一人の人間として見るのではなく、ある意味、完全な存在として見ているところがあるのだろう。親が親らしくない態度を取るのがどうしても受け入れられず、腹を立てたり、情けなく思ったり、大きな幻滅につながったりもする。
親を一人の人間として見るような視点が出てくると、親には頼り切れなくなってくる。相手にもできること・できないことがあるのだ、親は当てにならない、自分で何とかするしかない、という気持ちが強くなる。そうなると生活全般に自立した気持ちが出てきて、自分の力でやっていこうという気持ちがめばえてくる。自分らしいやり方、個性的なやり方が前面に出てくる。
何もこれは親に対してだけの問題ではない。例えば、自分の先生、尊敬している先輩や上司など、親的な関りを持っている人との関係にも当てはまる。相手が自分より経験がある、年長者だ、地位が高く肩書のある人だ、有名な人だ、だから何も考えず従っていれば間違いないというのでは、いつまでも親の言うことをそのまま聞いている子供と同じだと思う。右も左も分からない初心者のうちなら、相手のいうことを全面的に聞くような態度も必要かもしれないが、ある程度成長したなら、自分で考えるような態度も必要ではないか。カウンセリングも、相談に来た人には一緒に考えましょうと伝える。クライエントに全面的にカウンセラーの言うことを聞けと言うのではない。それぞれがそれぞれに考えて話し合うことが重要で、そこに新しいものが生まれてくる。カウンセラーだって同じである。スーパービジョンに行きさえすればいい、スーパーバイザーの言うことを何も考えずに聞いていればいいというものでもない。自分自身で考えることが必要だ。クライエントの前に座れば自分しかいないのだ。後ろからスーパーバイザーがアドバイスしてくれるわけではない。スーパーバイザーを査定するぐらいの気持ちも必要だと思う。相手を絶対の存在として見るのは、自分を失くすのと同じである。
先日、ユングの「自我と無意識の関係」(C.G.ユング著 野田倬訳 人文書院)を読んでいたら、「素朴な人間は、両親とは自分が見ている通りの人物である、とむろん信じ込んでいる。両親のイメージは無意識的に投影されている。そして両親が死んでも、投影されたイメージはあたかもそれ自体で存在している心霊であるかのように生き続ける。原始人たちに言わせると、それは夜になって戻ってくる両親の霊であり、現代人はこれを父親もしくは母親コンプレックスと呼ぶ」と書かれていて、いろいろ考えさせられた。精神的自立のためには、心の中にある親(あるいはそれは本当の親ではなく、親のようなすべての存在、親のように依存している存在すべてとも言えるだろう)への幻想を見直す必要があるのだろう。そうやって私たちは自分の足で歩けるようになるのではないか。
そんなことを考えていたら、村上春樹の「海辺のカフカ」を思い出し、あれは精神的自立の話だったのだと改めて思った。父親殺しから物語は始まる。父なる存在を内的に殺すことから主人公の歩みがスタートするのだ。物語の最後に母親的な存在との近親相姦的なイメージが出てくる場面があるが、これはいわゆる“近親相姦願望”ととらえるべきではないと思う。こころの中に生きていた絶対的な母のイメージ、つまり母性を求める気持ち、「両親が死んでも、あたかもそれ自体で存在している心霊のように生き続ける、原始人に言わせれば夜になって戻ってくる両親の霊」であって“the mother”ともいうべきもの、そしてそのような絶対的なものに対する関係性が、精神的自立にともない、ひとりの人間としての母“a mother”になり、最終的には“a woman”つまり親もひとりの人間・女性であるという側面が見えてきて、人間関係の在り方も依存的なものから対等なものへと変わっていく過程を象徴的に描いているシーンとして考えるべきではないか。
「海辺のカフカ」の主人公は10代の男の子だが、いくつになっても精神的自立は大きなテーマとなりうる。自分の場合だと、前室長の西村洲衞男先生の“心霊”にとらわれすぎてはいけない、ということだろう。どう自立するか、改めて考えるべきだと感じている。