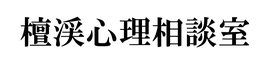長谷川泰子
西村先生の未発表の文章の掲載を続けている。改めて文章を読むと、西村先生は理論に盲目的に従うのではなく、自分なりに考える人だったと思う。シュピーゲルマン先生へのメールも、先生がいくつになっても自分なりの道を自分なりに探していこうという芯の通った姿勢を感じた。力の入った先生の文章を続けざまに読むと、自分で何か書く自信がなくなってしまう。
ずいぶん昔、ある作家が賞を受賞した後に書けなくなって苦悩した話を読んだことがある。私が中学生の時だったから、もう40年ぐらい前の話だ。その作家は高校生である文学賞を受賞し注目を集めたのだが、その後それがプレッシャーになり、原稿を書こうにも書けなくなってしまったという。毎晩部屋の中をうろうろと歩き回り、その気配を察した祖父母が気の毒がって、もうやめさせたらとどうかとまで言っていたという。本が好きで、夢中で物語を書いてきて、なりたくてなった作家だが、皆の注目を集めたとたんに自分の書くものが本当に面白いのか分からなくなってしまった。部屋の中を毎夜うろうろと歩き回り悩みに悩んだ挙句、ふっと「私は私だ」という考えが浮かんできたのだという。それは夜中に思わず「そうだ、私は私なんだ」と大声で叫んだぐらい大きな“発見”だったらしい。有名な作家はたくさんいるが、自分はその誰でもない、私は私で、自分の文章を書けばそれでいいと思ったという。それからは気持ちが楽になり、原稿が書けるようになったのだそうだ。
「私は私だ」というのは当たり前と言えば当たり前のことだが、悩んだ末に自分で見つけた答えだからこそ重みがあったのだと思う。たまに、カンセリングに来る人の中に専門家のアドバイスや助言通りにやればうまくいくと考える人がいる。もちろん、常識的な範囲内でのアドバイスや助言は必要に応じて行うが、大事なことは自分で自分の道を探し出すということだろう。たまたま誰かから聞いた言葉でも、それが自分で見つけ出したものなら意味を持つが、誰かから一方的に与えられただけのものだと、一時の仮の安定にしかつながらない。カウンセリングはその人が自分で納得できる方向を見出す場であり、私たち臨床心理士は、相談に来られた方ができるだけ自由に自分の道を探し出すお手伝いをする仕事をしている。地図もないジャングルに一緒に入って、広い世界につながる道を協力して探しだすような感じだと思っている。
先日、村上春樹のエッセイ「猫を棄てる 父親について語るとき」(文藝春秋)を読んだ。村上春樹が亡くなった父親について書いたエッセイだ。最後に書かれていた文章が印象的だった。「我々は、広大な大地に向けて降る膨大な数の雨粒の、名もなき一滴に過ぎない。固有ではあるけれど、交換可能な一滴だ。しかしその一滴の雨水には、一滴の雨水なりの思いがある。一滴の雨水の歴史があり、それを受け継いでいくという一滴の雨水の責務がある。我々はそれを忘れてはならないだろう。たとえそれがどこかにあっさりと吸い込まれ、個体としての輪郭を失い、集合的な何かに置き換えられていくのだとしても」(原文には“受け継いでいく”の部分に傍点あり)。
西村先生のような強烈な個性を前にするとひるんでしまうところもあるが、固有ではあるが交換可能な一滴として、あるいは交換可能だが固有な一滴として、自分なりの道を探していきたいと思った。