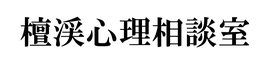心理臨床学(Japanese Journal of Clinical Psychology)第5巻第5号(2005年9月)に掲載された文章です。
金剛出版の許可を得て掲載します。
臨床家のためのこの一冊
『ソロモンの指環 動物行動学入門』
コンラート・ローレンツ著
Lorenz, Konrad
(日高敏隆訳) 早川書房
西村洲衛男
1
「臨床家のためのこの1冊」と言われて,自分のためになった本を挙げてみた。きだみのる著 『気違い部落周遊紀行』,今西錦司著『人間社会の形成』,宮本常一著『忘れられた日本人」,司馬遼太郎著『アメリカ素描』,津守真著「保育の体験と思需ー子どもの内的世界の探求』,そしてここに取り上げるコンラート・ローレンツ著『ソロモンの指環」など。驚いたことにこれらの本は著者のユニークな発想によってかかれたもので,参考文献がないのである。どれも大体は一般向けの本であるから参考文献がないのは当然であるが。今,気にかかっているレオ・カナーの自閉症に関する最初の論文「情緒的交流の自閉的障害』にも引用文献や参考文献がない。ローレンツの最初の論文は鳥の観察事実に基づいた思索であり,まとめは読者にとっても心に納めるためのものになっている。心理臨床の事例研究の論文が既存の心理学的な理論によってまとめられるのと大きな違いである。
私が好きになる人たちは,実際に現場の経験をして,その経験から本を書く人である。司馬遼太郎の「アメリカ素描』はよく文献を調べた上で,現場を訪ね,その時代のその情況を再体験するようにして書かれたもので,文献からだけの思索と大きく異なっている。自分の体験とそこからの思索を文章にしていくといわゆる科学的な学術論文になりにくいのではないか。これらの人は自分の考えを世に出して認められたが,私のような者がこのようなことをすると,自分の社会性のなさをさらけ出すだけである。恥ずかしい限りであるが,私のような人もあると思うので,少し書かせていただく。
自分を省みると,私もまたユニークで頑固な人間なのだと思う。文献研究をし,それらと関連づけながら,研究結果を考察し,討論していくことは私の苦手とするところである。こんな私は世の中で上手く生きていくことができないのだが,それは仕方がないことである。でも,自分の生き方で進みたい。私は外向的な態度ができていないから,文献の引用が下手だし,他の人がすでに指摘していることと,私が見出したことが同じならば, それはもう言う必要がないと思いがちである。先人にあやかったことを書いて自分を同列に連ねるよりも,自分の経験を意味あるものにして自分の意見を出すことこそ先人への礼儀ではないかと考える私である。このような生き方はある人から考えると大変不遜なことかもしれないけれど,ユングの個性化を考えるならば,私の生き方も悪くないと思う。特に,児童養護施設で生きる子どもを前にするとき,自分の経験に基づいた意見をもっておかなければ,彼らに通用しないように思うのである。彼らは必死に生きようとしているし,他人の生き方など参考にする余裕はないからだ。
結婚して中年になると長年住み慣れた家を改築したくなる。それと同じように,長年自分が依って立ってきた心理学の理論を自分の経験に基づいて書き直してみたい人は多いと思う。私は60近くなってから,長年親しんできたユング心理学を基礎にして自分の心理学,西村心理学を作りたくなった。その方が自分の心理臨床に合うし,心理臨床を続けていて絶対楽しい。毎日の仕事で発見の喜びがある。これが学問の楽しみではないかと思う。暗い話を聞く仕事が明るくなるのだ。司馬遼太郎は『アメリカ素描」の冒頭で,井上ひさしの言葉として,「文化は第二の子宮である」 と書いている。臨床心理士は臨床心理学の理論という文化に守られて生きている。理論は自分の城であり, 住み慣れた家である。借家でも住み慣れた家は自分の家だが,経験という財産を使って自分の理論を作り,そこに住まうのはーつの賛沢であろう。
2
先に述べたように私がよい本だと評価するものは,著者の経験と思索から書かれ,しかも,専門外の人にもわかりやすい本である。児童養護施設での子ども体験を希望する学生には津守真著「保育の体験と思索」をまず読ませる。この本を読むと,子どもにどうかかわるか,観察の姿勢,どんなことが観察されているか,観察したところからどんな思索がなされるかがわかる。この本では,何よりも,子どもたちに愛情を持ってかかわり, 生き生きと遊び,子どもに自由な行動を許し,共に動きながら,子どもの心の中に形成されていく心の機能が考察されている。この本は子どもへのかかわり方や考察の仕方がわかる実習の教科書である。この本には幼稚園時代の,障害児のことも含めて書いてあるので,遊戯療法を理解したい人にはよい参考書となるだろう。
3
京大病院で笠原先生について勉強していた頃, 心理室に鳥居智子さんがいらっしゃった。彼女は神谷美恵子先生の教えを受けた人で,暖かくて聡明な感じは神谷先生を感じさせるものがあった。彼女がこんな本があると紹介してくれたのがコンラート・ローレンツの『ソロモンの指環」であった。その本は早川書房の新書版で出ていて,ミステリーの本と共に並んでいたので,題名からミステリーと混同されると思った。ところが,ハヤカワ文庫にもドキュメンタリー・シリーズがあったのである。その中の1冊で,後にハードカバーでも出たが,今では文庫本サイズになって,動物行動学入門と言葉が添えてある。この言葉がないと, ハヤカワ文庫ではミステリーと間違われても仕方がない。
原題は「彼は獣や鳥や魚と話した」というものだが,この言葉は旧約聖書列王記(「彼は獣や鳥や魚について語った」Ⅰ 4・33)に由来する。ローレンツは,獣や魚について語っているが,彼自身は動物の言葉を覚えて話したというのである。読者も同じ感想を持つだろう。
私たちは,悩みを持つ人のことばを憶え,思考形式を理解して接している。私たちはその専門性によって,普通の人から見たら不可解な解離性障害の人や不登校の人と話していけるのである。その人たちも,同じ人間であるが解離性障害とか, 不登校になるパーソナリテイを一部に持っているから人から理解され難い。そこを理解し,真摯に接することに臨床心理士の専門性があるのではないか。動物の行動を外からより客観的に観察する現代の動物行動学とは異なっているかもしれないが,動物の言葉で動物と共に境界なしに生活したローレンツの研究はとりわけ臨床心理学に示唆的であると思う。
4
ローレンツは動物と会うのに面接の構造など設けないのだ。彼は家の中にネズミや鳥を放し飼いにし,果ては刷り込みによって親子関係になってしまった動物たちと共に暮らして研究した。その様子が生き生きと書いてある。彼は現代の心理療法家から見れば境界例である。動物と人間の境界がはずされているのだから。しかし,読んでいて少しも境界例という感じがしない。なぜかと言えば,愛と,礼儀が感じられるからだ。動物に対して相手の性質に添って接するとき,そこにきちんとした関係ができ上がる。人間関係でも,礼儀をわきまえて接すれば,相手も礼儀を感じるはずである。ローレンツが動物たちとの共生の中で,多少の限界設定をしながら,ある折り合いを見出したように,私たちは人々の性格を知った上でのおつき合いを進めていくべきではないかと思う。
今は流行らなくなったが,学会で境界例の事例がたくさん発表された。今は嘘のようにない。なぜだ。私は次のように考えた。今流行りの解離性障害,つまり,ヒステリー性格の人に共感的受容的態度で接すると,その人はどこまで甘えていいかわからず混乱し,治療者を悩ませる。その結果,境界例と診断されること間違いない。境界例の多くは,治療者の共感的受容的態度が解発刺激になってヒステリー性格の人の不安を引き出したのである。これを転移と考えることもできるが,治療者の共感的受容的態度が作り出したものと考える方が簡単である。来談者中心の受容的な態度がヒステリー性格の不安の解発刺激であることは,さまざまな事例で見ることができる。最近は境界例に接したら厄介であると考えて治療者は敬遠するようになった。この治療者の敬遠的な態度が境界例的な人にとって安らぐのである。このために最近嘘のように境界例が報告されないのではないか。
最近まるで傾聴ロボットのように面接しているカウンセラーに出会うことがある。ただ間違いのないように傾聴だけの面接をしているのである。これは訓練され資格を持った人の行動特性のーつで,マニュアル行動の形式である。管理社会ではこれが普通になってきているのではないか。心を用いない傾聴ロボット面接である。クライエントに「私の今までの話を聞いてどうお感じになりましたか」と問われて,「あなたはそういうことが心配になるのですね」 と受けるのだ。マニュアル行動を剥ぎ取ったとき何が残るのか。何も残らないのではないか。マニュアル行動が専門家の自信を支えるものになっているのではないか。これは大学院で刷り込まれた行動様式ではないだろうか。
人間関係の現れ方を幼少期の親子関係の反映,つまり転移と考えることもできるが,人が経験によって学習した動物的行動様式と刺激・環境という点から事実に基づいて考えることもできる。アスぺと呼ばれている生徒が中学3年になって,何事も母親に質問するようになって,母親は困った。この行為を強迫的な常同行為と見るよりも,高校進学を前にして,その不安から質問による母親への愛着行動が解発されたと捉えた方がわかりやすく,母親も治療者も安心して援助できるのではないか。
5
読者の一人は,「語りかけられている三つの動物のどの部類に,人間である自分を算入すべきなのか,さっぱりわからなくなってしまった」と感想を述べている。ローレンツは獣にも鳥にも魚にも共感能力を持った人であった。このように余りに人間心理的に動物を理解したので,そのことで批判されたらしい。ローレンツは次のように述べている。
「… 私は決して擬人化しているわけではない。いわゆるあまりに人間的なものは,ほとんどつねに,前人間的なものであり,したがってわれわれにも高等動物にも共通に存在するものだ,ということを理解してもらいたい。心配は無用,私は人間の性質をそのまま動物に投影しているわけではない。むしろ私はその逆に,どれほど多くの動物的遺産が人間の中に残っているかをしめしているにすぎないのだ」
動物的遺産が人間の中に残っているのを発見しただけなのだとローレンツは言う。これと同じ考え方がユング心理学にあるではないか。普遍的無意識である。ユングはローレンツを読んでいたかどうかわからないが,普遍的無意識の中に人間以前の動物的心性も残っていることを考えていた。ただ,彼の元型の概念は多様な行動様式を受け入れるにはあまりに狭かったのではなかろうか。
フロイトの無意識の概念は個人的無意識であるから,動物的遺産が組み込めるところはエスとリビドーである。これでは動物行動学を取り入れることはできそうもない。
6
『ソロモンの指環」から,さらに『攻撃ー悪の自然誌」を読んで,動物の行動様式の進化と人格の発達との並行性を私は考えるようになった。ここでは動物の攻撃性の進化が語られている。無名の群れから,個性を持った集団へ,個性はある程度もったが,未だ攻撃性を統制できず,縄張りを持ったり,離れて暮らすことによって統制が取れているもの,最終的に攻撃性を完全に統制できたものだけが,真の信頼関係を保つことができるという主張が私は気に入った。
この考え方を,人間の人格の発達に関連づけて考えると面白い。子ども時代から人は個性を持っているが,攻撃性の観点から見ると,まだ十分に個性は発達していない。思春期の段階も未だ個性がなく無名の群れに近い。中学生のアイドルへの―様な熱狂を見るとわかる。この段階では対立はほとんど起きない。個性がないと同時に相互の攻撃性も少ない。中学3年くらいになるとわれわれ意識が芽生えはじめ,集団の喧嘩が始まる。大学紛争当時流行った学生の集団相互の戦いはこのレベルのものであろう。未だ一人一人の個性はない。今学生運動はないけれど,われわれ意識を持つグループが個性的集団になったとき,人は対立を意識するだろう。多少個性を持った学生は,同じキャンパスにいるために恋愛し,あるいは,互いに反目しあったりするだろう。その関係は卒業し, 互いに離れると自然と解消してしまいがちである。ローレンツのいう同じ場所にいるからくっついているという「場所婚」が大学ではよく見られる。相手の個性を認知し,お互いの攻撃性を完全に抑制できるには,人間は相当に長い間の経験とその反省を必要とする。攻撃性の進化が,個体相互の信頼関係の形成に深く関係しているとローレンツは言う。完全に攻撃性を統制できたものだけが生涯変わらぬ連帯の絆をもつことができるという仮説は夫婦関係を考えるのに大切である。人格が未発達であれば,攻撃性も未発達である。そのレベルの夫婦や親子の関係は調整が難しい。問題は攻撃性の認知と抑制である。
私たちの習慣的な行動様式,つまり人格の中には,刷り込まれたと言いたいようなものが多くあるのではないか。とすると人格の変化は難しく,コンプレックスの解消とか人格の変化を考えるよりも,刷り込まれた性格を持ちながら,困難をいかに避けて生きるかと考える方が現実的かもしれないのだ。コンプレックスの解消には言語化が重要というが,それは鳥類の気分の表明としての言語ではなく,他者に真意を伝え,自分とその状況を客観視することを含んでいなければならない。心への敏感さと客観性こそロジャーズが重要視したものではなかったか。
7
津守の『保育の体験と思索」と同様,ローレンツが一般の人向けに書いたこの本を読んで,私は生きるものへのかかわりの姿勢,そして観察と思索の仕方を教えられた。共に生きていくという愛情のかかわりの中で体験され,その体験を意味のある経験に高める思索がある。今や動物行動学はすでに変貌し,ローレンツの方法や考えは時代遅れと言われるが,ローレンツの体験と思索は心理臨床家にとってとても有意義であると私は思っている。
<次へ 前へ>