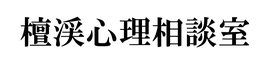同じ日付でほぼ同じ内容の「真相分析法について」という文章もあります。細部で異なった表現があるため、両方ともそのまま掲載します。(スタッフ)
1 はじめに
今年になってやっと、本当に自分らしい心理療法に達したと感じるようになった。それを真相心理療法と呼ぶことにした。
この心理療法はクライアントの真実を明らかにするという点で河合の心理療法と同じなのだが、やり方が違う。河合はクライアントの真実を明らかにするためにできるだけ何もしない態度で接する。私はクライアントの真実を明らかにするためには何でもするという点が異なる。何もしないと何でもするでは、方法が大きく異なる。
私の真相心理療法はクライアントの真実を明らかにするために真実の話し合いをする。何が真実かわからないから手探りで進むほかない。心の真相はひとかたまりのようなものではなく、その人の生活環境、生きてきた経験、これから待ち受けている未来の状況、そのような過去現在未来とその心理的空間を全て包含しているから、これだとまとめてつかむことはできない。その作業はまるで玉ねぎの皮むきで中々真相にはいたらない。しかし、玉ねぎの中心には素晴らしい可能性があって、そこに至ると生きる望みも元気も湧いてくる。実際に玉ねぎのような球根は中心の細胞に全ての可能性が詰まっていて、そこからまた同じ球根の植物が芽生えてくる。豪華なシンビジュウムはそうして作られる。
心の真相は何か不明だが、真相に向かい合うと安心感とエネルギーが湧いてくる。心理療法の目的は安心感と生きる意欲を見出すことだから目的と方法が合致している。
2 世界観と云う心理の地平
いつの時代も人々は世界観の地平に立っている。
世界観が変遷するというのは天動説から地動説への変化を見ても直ぐにわかることだが、地動説を学んだ私たちは、地動説は正しいのだとそこでひと安心する。しかし、そこに相対性原理なるものが出てきて、空間が歪む可能性が出てくると、単なる地動説だけでは安心できなくなる可能性が出てくるのだが、実際生活にはあまり影響がないから、ひとまず安心しているにすぎない。
宗教は人々に安心感と生きる意欲を与えるためにある。すでに確固とした体系を形成した仏教やキリスト教は、妥当な戒律を失ってしまい本当に苦しむ人々の頼りにはならない。本当に悩む人の頼りになるのは新興宗教である。あるいはイスラム教のように厳しく戒律を守って宗教を奉持している場合は不安が少ないはずである。しかし、イスラム教も考え方によって宗派が違って来ると、考え方の違いによって対立が生じやすくなる。個性的になるほど普遍的な関係を保つことが難しくなると、ローレンツ、Kは考えた。しかし、人の安定感は世界観や人間観の共有によって生まれるのではないか。
私たちは時代精神というその時の世界観や人間観を漠然と信じて安定している。
私たち心理学者はフロイトやユングが開いた心理学の世界に入ることによって安心しているのではないか。しかし、そこから出てしまった私は自分の心理学を作らなければならない。それは自分にとっては正しいが、普遍性は持たない、極めて個人的なものである。
3 心理学の変遷
今は、認知行動療法が流行る時代である。
私が大学生の頃、50年前は知覚と学習の心理学の時代であった。ある人は知覚の恒常性の研究をして論文を書き、研究者として大学の教員になることができた。ある人はネズミの行動の研究をし、ある人はグループダイナミックスの研究をして研究者になることができた。それらは認知と行動の心理学で、その後深層心理やイメージの心理学に取って変わり、それがほぼ30年位続いて、今の認知行動療法になった。この認知行動の心理学の時代が後30年位続くのではなかろうか。
だから、私が行き着いた真相心理療法の考え方は今の時代には全く理解されないか、とんでもないものとして排斥されるたぐいのものである。
私たちの心理学の世界では、フロイトが無意識を発見したというか発明したというか、20世紀の初めに今までにない新しい心理学が開かれてきた。神が作ったという人間を、身体だけでなく心まで、生理学的な目で見て、客観的な研究の対象とした。科学技術の発展と相まって、精神分析は世界に広まった。
フロイトが作り上げた精神分析から派生して、ユングの分析心理学、アドラーの心理学、クライン心理学などが発展してきた。それらは共通して意識、無意識を基礎としているのではないか。フロイトは無意識の願望が意識の活動を阻害することを例に挙げて説明し、ユングは、人々の太古の経験が集積した無意識から生じたイメージが意識に影響を与えると考えた。
無意識は意識に対して問題をもたらすから意識の主体、自我は無意識と相対して無意識と調和を図ることが心理療法の課題であるとフロイトやユングは考えたのである。
フロイトもユングも、無意識を意識・自我にとって言わば悪者とみなしてきたといえるのではないか。
それに対して、20世紀のはじめ『科学と方法』を著した数学者ポアンカレは、無意識は意識より賢いという説を立てた。数学上の発見は無意識からの問題解決の糸口の浮上によってもたらされるからである。無意識からイメージや考えの浮上によって人々の考えができていくという考え方は、ユングのシンクロニシティと同様不可思議な、合理的な考えによって説明できないこととしてほとんど顧みられることがなかった。
フロイトの『夢判断』の直ぐ後に公にされたウイリアム・ジェームズの『宗教的経験の諸相』は多くの人々の注目を浴びたが、科学技術の発展の陰に埋もれてしまった。科学技術が宗教に取って代わったからであろう。
しかし、フロイトの無意識の心理学精神分析もユングの普遍的無意識の心理学も一つの考え方である。それなら、それらとは違う心理学もあって良いはずである。フロイト派の人は精神分析を、ユング派の人はユング心理学を信じている。それを乗り越えるのは、宗教の宗派を変わるくらいに難しい。人間観が違うからである。
見方が違うと全く違う世界が開けることは次の例でわかる。
数学の世界では、私たちが中学でならったユークリッド幾何学と非ユークリッド幾何学がある。ユークリッド幾何学は私たちが常識としている2次元の平面で成り立っている。平面上で1本の直線に対して並行は直線は1本しか無い。非ユークリッド幾何学は球体や双曲面で平面を考えるので、球体の場合は、平行線は1本も無いが、双曲面では無数にあり得る。このように平面の考え方が違うと違った世界が開ける。双曲面の世界は常識ではイメージしにくいが、球面の世界は地球が丸いので、飛行機が飛ぶ最短距離の航路が直線と考える時に成立しているのである。
心理学も考え方も人についての見方を違えると違った世界が開けるはずである。
4 人についての見方
A 生態学的視点
人は家庭の中に生まれ育ち、父や母、きょうだい、父母それぞれの両親(祖父母)、おじ・おば、いとこなど親族関係の中で生きている。生まれ育った地域の文化にも国の文化にも包まれて生きている。「文化は第二の子宮である」(井上ひさし)。
家庭の中は平和であって欲しい。
しかし、生まれ出てきた時は両親はすでに離婚していたということもある。
両親がいつも言い争っていて、争いのさなかに育って来ることも少なくない
あるいは、嫁姑の闘いが続いて、おばあさんや母親の愚痴の聞き役をずっと続けてきた人もある。国内戦争の最中で自分を育てていくのは難しいけれど、愚痴の聞き役は更に大変である。子どもは親に代わって悩み、自分を育てる間がない。
今西錦司は生物の住み分けを最初の研究テーマとしたが、家族のなかの住み分けがどのように行われているか考えねばならない。人間のような個性を持った生物はその土地の文化に応じて適当に住み分けることが大切である。
B 生まれたときにもっていたもの-体格、知能や性格など
人には丈夫に生まれた人、虚弱に浮かれた人、知能の高い人低い人、気性の激しい人穏やかな人など、様々にある。
児童養護施設などで見ると、生まれ落ちてすぐに乳児院に入って育っているのに、国籍の違いを感じさせるものをもっていることがある。
C 経験の蓄積としての人
人は生まれ出て来たとき、目を大きく真ん丸に開いて世界を見ていると小児科医は言った大きなまん丸の目で見た親の顔は喜びに満ちていただろうか、それとも不安や緊張にこわばって見えていただろうか。
最近の知見としては、胎児はお腹にいるときから母親の声を聞いていて、母親の声には敏感に反応することがわかっている。だからお腹にいる時から母親の感情の浮き沈みもみんな経験しているに違いない。
授乳は喜びのうちになされただろうか。ある人は、お乳を飲んでいる時、この人、母親は授乳することが嬉しくないと感じたという。そういう原体験を持った人は早くから自立しなければならない。
幼いころ私が母親の膝にまといついているとき、隣のおばさんに、この子はいつまでも自分で立つことができない棒杭みたいだと言ったのを覚えている。その時いつまでも母親に甘えている自分が非難されていることを意識すると同時に、それはあなたの責任でもあるではないかと感じたことを覚えている。私にはそんなに幼い頃から状況を見る目があったようだ。甘えている自分とそれをどこかで見ている自分と分かれているので、私は経験を半分の自分でしかしていないのではないか。何か足りないのはそのためではないかと思ったりする。
一つの心でしっかりといのちを経験している人とあまり経験していない人があるのではないか。
人生の様々な経験というけれどあるところは強くあるところは弱いということもあるかもしれない。
D 親との同一化によって受け継ぐもの
人は親との同一化によって成長してくる。ある人は父親と、ある人は母親と同一化していて、その親の願望も取り入れていることが多い。
男の子は母親と、娘は父親と同一化しやすい。
ある女性は第一子で長男を期待されたが、妹もできて、男の子だったら良かったのにと思われ続けた。その結果、何かしら男性的な性格があって、結婚しても妙に夫を異性として受け入れることができないという。友達のように仲良しだが、性的な雰囲気になることができない。親との強い同一化はポジティブにもネガティブにも出てくる。
親の性格は子供に影響して来る。
家裁の調査官が非行少年の親に聞いていると、親も子供の頃そうであったということは珍しくない。離婚調停に出てくる親が双方とも離婚歴があることも珍しくない。
小学校高学年まで夜尿を引きずっている子どもの親に聞くと、親もまた子供の頃夜尿症で悩んだと語られることがあった。学校で腹痛に悩む親が出勤時に腹部の症状でなやんでいることは珍しくない。不登校の子どもの親がまた不登校を経験していたということも珍しくない。
このような問題は体質の遺伝なのか、性格の受け継ぎなのかわからない。問題はそれぞれ個人の問題のようでありながら、家系的で、上の世代から背負わされたもので、その個人の責任ではない。しかし、問題の解決はというと気づいた人が悩み考えて克服していかねばならない。そのように悩み克服すると、次の世代も問題を悩み克服するという習性が受け継がれていくのではなかろうか。
E 心の層
われ思うにわれありと云う思う私がある。私という主体がある。これを自我心理学では自我というが、自我とは自分のことで、自分は生き方や見方や態度などを持っているので何らかの心理的な質量があるのかもしれないが、見えないのでわからない。自我とは私という意識する中心の点かも知れない。私は長い間、自我ということがわからなかった。ある時、土居健郎の『精神分析』を読んでいると、自我とは自分のことであると書いてあったのでホッとしたことを覚えている。土居健郎も自我について自我とは何かと考えたに違いない。夏目漱石を研究した人だから、『吾輩は猫である』の我輩とは自我であると考えたに違いない。
仏教には小我と大我があって、自我は小我に当たるだろうか。私は仏教に詳しくないからわからない。
自我、私は大海に浮かぶ点のようなものではないか。大海にはいろいろな思い、考えや感情、衝動や意思、希望、などなどいっぱいある。それらは点のような自分がよく目を凝らすと見えてくることがある。
意識は心なのか。意識は私が何かに気づく時の意識の機能らしい。意識が働かない時無意識というのではないか。無意識は大海のようなもので色々な思いや経験が漂っているのではないか。そこにフロイトは意識と無意識とを作った。意識には知性や記憶などわかっているものが属している。そのうちでとりわけ言葉は重要である。言葉にならない、わからないものが全て無意識となる。無意識は忘れられた個人的経験内容というフロイトの考え方と人類が進化してくる過程で経験したもの全てを含んでいると考えるユングの考え方がある。
夏目漱石は小説『吾輩は猫である』を書いた。吾輩は世間を超越した視点を持つ内的な主体であり、主人は世間に生きる社会的ペルソナを持った人間である。その人間を猫、吾輩は見ている。文化の中で行動する人間とそれを斜に見ている観察的な意識の主体を描き出したという点で漱石の考えは心理学的である。
そう考えると、心には意識の主体としての私、吾輩と、感情や衝動という情緒や欲求衝動を生きる私があり、感情や衝動が湧いてくるところのもう一つ深い心の層があるのではないか。それは人間が動物として本来もっている心、動物的な心であろう。ユングがサイコイド、psychoidと呼んだものはそれではないか。
私たちが何かしようとする時、それはヤバイと時に感じる。そのヤバイはハッキリとそれがわかることもあるけれど、いつもは、なんとなくかすかな声でささやいてくる。このささやく心ははっきりせず、直ぐに忘れ去ってしまう、記憶に残らない意識である。この層の心を金岡秀友は阿羅耶識と説明している。唯識論は私には理解できないので、金岡秀友の説明に頼るしか無いけれど、この記憶に残らない意識は心を探求する上で頼りになるので、大事にしておきたい。これはフロイトの前意識とも違うし、ジェンドリンの前概念的なものとも違い、ある思いや考えや行動に対して仄かな影のごとく生じてくる心である。
今の私のあり方生き方に対して、夢が現れる。夢はどこから現れるのか。フロイトは夢には隠れた願望が現れると考えたが、その夢がどこから現れるかは考えなかった。フロイトが考えた夢の源泉は過去の経験、忘れさられたものの集積であった。
夢を送り出す心は人の動物としての心であって、それが知性的な自我に対してメッセージを送っていると仮定する。
夢を送り出す心は一番深層にあって、今その人にとって大切なものに気づくように送り届けてくれるのだと思う。夢を見た人の人格と夢のメッセージを対応させて見ていてそう感じるのである。
夢は全ての人が毎晩見ているが、その夢を記憶する人としない人がある。
夢見る人は自分を省みることができ、夢を見ない人は自分を省みないひとである。
以上のように考えて、私は心の構造を次のように考えてみた。
人格と夢見る心の2つである
人格は意識する主体を持ち、感情や衝動を感じ、これまでの様々な経験も保有し、周囲との関係を生きる思考パターンや行動パターンを持ったものである。
夢見る心は、人格の下の深層にある人間の身体も含めた、つまり人間の動物的な側面も含めた心の部分で、ここに全体的に調和を図る中枢機能があると仮定する。この部分は全くわからないところだが、幾分は夢によって、あるときは空想や想像にによって、子どもでは自然な遊びに現れてくる。箱庭遊びも、それがその時その場の遊び心で行われているなら夢の心を反映していると思われる。
F 心の表現手段
心の真相を明らかにするためには様々な表現手段を用いることが出来る。
言葉、イメージ、症状、行動、行動は関係性を含む
言葉はうわ言以外は考えてしゃべるわけだから意識の関与が強いけれど、意識を弱めて、心のなかから自然に浮かび上がってくるものを口に出していると意外に深層の心に触れていることがある。初回面接ではできうる限り思いつくままに語ってもらう。そうすると問題のあり様が漠然と浮かび上がって来ることがある。
イメージは夢をはじめとして、意識の関与なしに出てくるものほど内的な真相を反映しているであろう。子どもの場合、遊びは特に象徴的である。箱庭制作も遊び心でやってもらうほど、その人の状況がよく反映されている。
身体症状は身体的病として出てくるから、ほとんど意識の関与がない。だから、身体症状の背後には真相の意味があると考えて良い。最近の身体医学は身体の病を全て身体の生理で考えるけれど、心理の立場としてはその心理的な意味を考えることも大切である。病も気からと昔から考えてきた。現在の身体医学はこの考えを全く無視してしまっている。心理の立場から病気の心理的な意味を考えると、医師は医学領域に入るなというけれど、今は気の病という領域を医学は放棄してしまっているのだから、心理領域で病の意味を考えて良いのではないか。
行動は、主に非行・犯罪領域である。ものを破壊する。放火、盗み、強奪、殺人などその背景には心理的な意味がある。私は幼いころ野の花を摘んでいた。きれいな花を折り取る癖があった。青年期になっても道端の草の穂をしごく癖があった。アイデンティティの心理学を学んで初めて、自分の幼い時からの癖が自分が否定されて育ったことを示唆していることに気づいて愕然とした。自分はどこかでいつの間にか去勢されていたと思っていた。ところがアメリカで分析を受けた時、分析家シュピーゲルマン、Mから、お前は自分で去勢したのだと指摘を受けた。分析家河合はそういう指摘はまったく行わなかったが、シュピーゲルマンとは、ディスカッションができた。
行動は人間関係に現れて来ることがある。
親が非行したり離婚したりしていると子どもがおなじことを繰り返し易いと先に述べたが、非行がおこるのは親の躾が厳しいからということもある。非行を経験した人は成長して堅気になる。堅気になって躾が厳格になる。そういう親に子どもは反発して、非行が繰り返される。
離婚するとき親も出てきて子どもを取り込んでしまうことがある。子どもが自分で話し合う力がなく、親が乗り出してくる。そこでは夫婦二人での会話にならない。
あるいは相手に対して不満を感じているとき、不倫をしてしまう。不倫をしなければならない不満な関係が背後にある。そういう外れた行動の背後の真相を明らかにすると、何か解決の糸口が見つかるかも知れない。
私たちはクライアントの言動や夢や箱庭など様々な表現から真相を明らかにすることが出来るはずである。
G 文化のなかの人間
井上ひさしが使った言葉として司馬遼太郎は『アメリカ素描』の中で、「文化は第二の子宮である」と言っている。人は文化の中で安心して生きている。文化とは何か、心理学的に見るとそれは思考と行動のパターンであるということができよう。
私たちはそれぞれの文化の中で生きている。文化の違いを意識すること無く心理臨床に携わることはできない。
私たちは一個人の悩みという限られた事例に接するのだが、その個人でさえ、その人の背景にある文化を考えざるを得ない。日本で生まれ日本で教育をうけた韓国3世でさえ、韓国文化の中で生きていることがある。ましてや、ブラジルで育った日経2世の母親の心理を考えるとき日本の文化の物指で考えるのはクライアントのためにならない。
韓国人の家庭やブラジル人の家庭と比べると日本人の家庭は違う。韓国人家庭では父親の厳しさは凄いと思うが、父親が亡くなった後の母親の激しさは格別であった。子どもは親に逆らえないからである。この心理は核家族し、道徳的に親も自分も一人の人間だと考える日本人の家庭感覚では考えにくい。ブラジル人の母親の強さも日本人の理解を超えるのではないか。それは聖母マリアに厳格さを加えたようなものではないか。子どもの母親への服従は日本人の甘えでは理解出来なと感じている。母親が強いだけにそれで子どもは守られていると思う。
日本人も昔は家族制度の中で生きてきた。個人も大切だがそれ以上に家が大切であった。母親は夫の母親に仕えなければならない。そう考えて姑に支えてきた嫁は戦後の民主教育で育ち、親も子も本来平等という考え方で生きているし、最近の子どもたちはさらに家から離れていく傾向にあり、親は親、子は子という考え方になっていて、家の嫁として生きている女性は三代の間で苦しむことになる。学校社会で育った民主主義と親から受け継いだ家族主義との葛藤を親の介護の中で考えて行かねばならない。
家の嫁として過ごしてきた女性には夫婦二人で支えあって生きる夫婦愛は育っていないことがある。妻が夫に頼ることができないとき、妻はどこに頼るのか。私たちはそういう相談をうける。ことの真相は複雑である。
文化の問題は国により、また、時代の変化により違ってくるが、それは社会の問題ばかりでなく、個人の中にもあって、個人は文化という普遍的なものを生きていかねばならない。
文化は人の、あるいは動物がもっている行動パターンである。生物学では本能とも呼ばれる。本能は変わらないものであり、人間がもっている文化も変わりにくいものであることを知っておく必要がある。
文化について、誰が言ったかわからないが、次のような法則がある。
征服したものは征服したものによって征服される。
例えば、アメリカは日本を征服した結果、日本の文化である禅などがアメリカに流入した。
その後、日本は経済的に復興してアメリカの経済社会に侵入した。その結果、アメリカ文化が多く入って来た。
逆に、結果的に見れば、文化の改変には悩み苦しむ犠牲が必要になるということである。犠牲なしに文化は変わらないということであろう。
H プロセスとしての心
河合先生があるとき、心をどう考えるかと問われた。その時とっさにプロセスということが思い浮かんだので、心はプロセスですと答えた。心はこれといって掴まえることができないからである。随分立ってからあの時の答えが良かったと言われた。何がどうよかったのかぴんとこなかったが、後になって物語論が出てきた。心は科学的に捉えることはできないが、物語ることで捉えるという考えである。
その後、物語を研究することが流行って、源氏物語を研究する人も出てきたが、それはどこかピントがずれていると思った。
私は村上春樹の『1Q84』の第Ⅱ巻を読んだとき、これは河合隼雄の死を悼む追悼小説だと思い、その感激にかられてブログにエッセイを書いた。村上春樹がどんなに河合先生を慕い、自分の半生を語りたかったのかを感じた。先生の生前にそれができず、また、集中治療室にいる先生に会わせてもらえなかったために、小説の中で寝たきりの父親に半生を語るという物語を作り、その結果、小説の中でたましいが生まれでて来たのであった。それが『1Q84』第二巻の中心的な物語である。物語ることによって、村上春樹は、自分と河合先生の関係を捉えたと思う。
このことをエッセイに書いてブログに出した後、私は夢を見た。夢の中で、私は大川の横の水路に入り、そのヘドロの溜の辺りにいる小魚や虫を探していた。小川の中で小さな魚やカニを見つけるのは私の子供の頃からの習性である。
この夢は明らかに、私に小説の出処である心の真相をみだりに探るべきではないと警告していた。小説を生み出した心の作業場の真相はヘドロの水路にしか過ぎないと夢は警告していた。その物語作成の心の作業場の跡はヘドロの溜まり場で見ないほうが良い。小説家が出した物語だけを読んでいればいい。たましいの親にも例えられる先生の死に当たって自分の心の真相を描き出すと『1Q84』という物語になったのだ。それは幅00米もある水量豊かな大川であった。大河のような物語、つまりプロセスとして読んでいれば良いのである。
私は今年の心理臨床学会で、ガンで死んで行ったある女性の夢のシリーズを発表した。
一連の夢のシリーズは、はじめから終わりまで80ほどの夢を報告された順に並べて読んでみると、その夢シリーズの背後に、女性が自分の人生はこうでしたと物語っているのが何となく浮かび上がって来た。それがわかると、夢の解釈は何も必要が無くなった。いくつかのヒント、家族関係やお世話になった人々の思い出、結婚した夫との関係、そして、死を目前にして出会った男性とのたましいの関係などを念頭におきながら夢のシリーズを見ていくと、女性が死のプロセスをどのように生きたか、その物語が浮かび上がって来るのであった。物語は結果的にでてくるものであって、私たちにできることはイメージのプロセスを出すところまでであって、物語るところまでは行かない。それは小説家の仕事ではないか。心のプロセスは幾筋もあり、これといってまとめることはできない。中国の揚子江のように上流も下流も沢山の支流があり、水たまりも沢山できている。心のプロセスとはそんなもので小説家の物語のように一筋ではまとめきれない。心は確かに物語的にしか捉えられないが、夢や箱庭で捉える心は幾筋ものプロセスとしか言いようがない。それを物語として書くことも難しい。物語で描き出すとしたら、大河の支流が上流にも下流にも沢山あるようにいくつもの物語を作らねばならない。『城の崎にて』や『暗夜行路』などの小説を書いた志賀直哉の人生はそれらの物語から感じ取れてくるが、それも一部分にすぎない。人の一生を描き出すには沢山の物語が必要である。
5 カウンセラーの資質
心はころころ変わりやすいから心というのだとある人が言った。それは一面本当である。確かな心というけれど、心そのものが本来変わりやすいものなのである。ものの見方も人それぞれに偏っていて、自分の欲目で見ているからものごとが正しく見えない可能性が高い。だからカウンセラーにとって最も大切なことは客観性であると私は考える。ロジャース、C.Rははじめ、非指示的カウンセリングを発表したとき、カウンセラーの資質として第一に客観性をあげていたが、来談者中心療法になったとき、最初に上げた客観性を取り下げ、共感的理解を重視して、客観性を放棄してしまった。この時から、共感と受容の来談者中心療法は新興宗教のようになってしまった。
心を研究していくためには客観性は第一に必要である。
それは実際には疑い深い慎重な観察と言って良いものである。疑い深い慎重な観察とはラテン語religioの元々の意味である。神はどこにいつ現れるかわからないから慎重に観察し、現れた神について善悪を疑い、どう対処すべきか考えなければならない。このような神との出会いは、旧約聖書の出エジプト記のはじめ、モーセと神の出会いに描かれている。
精神分析的な視点やユング心理学的な視点に拠っていると、それらの理論的な枠組みから人を見てしまいがちになる。私はある症例で、棺桶の夢を見たとき、それを死と再生で考え、いずれ死んでいるものが生き返って来ると考えた。しかし、その棺桶はクライアントの死を予告するものであった。私がユング心理学にとらわれていなかったら、死の予告も意識屋に入っていたかもしれない。一つの視点でなく多用な視点で見る必要がある。
第二の条件は謙虚さである。
カウンセラーは自分の内外に起こることを客観的に広く観察し、それに基づいて見方をいつでも修正していく謙虚さが必要である。
この謙虚さは自我の強さの指標であるとクロッパー、Bは言っていたと思う。
自己の意見を強く主張し、突っ張る攻撃的な態度が自我の強さなのではない。状況に応じて慎重に謙虚に進む力が大切なのである。周りの人々の意見を考慮しながら、妥当な見方を探りだしていく力量が人々を引っ張って行くのである。
第三は、最も大切な要素で、人生を前向きに生きる意欲である。カウンセラーは生きることに喜びを見出していて欲しい。クライアントはこの世に生まれて来なければ良かったと思っている。ときにはもう死にたいと思っている。拒食症は静な自殺である。クライアントが死にたいと言った時、この世は絶対楽しいから、どんなことがあって生きていなさい、必ず幸せがありますと言える人であってほしい。その前向きに生きようとする意欲が無ければならない。どんな状況でも前向きに生きれば人生は開かれてくるという確信は、心を尽くして苦労し悩み生きた程度に応じて可能なことではないかと思う。
高い知的な能力と恵まれた環境でスイスイと生きてきた人にはない、苦労した人にだけ備わる特性であろう。
法華経に従地湧出品というとりわけ重要な経典がある。その経典には、世尊は、大地の裂け目から出てきたものに悟りに至るように勇気づけたと書いてある。
大地の裂け目から出てきたものとは、地下のくらいところで生き延びてきたもの、苦労に苦労を重ねて生きてきた人が価値ある人だと世尊は弥勒菩薩に説いている。弥勒菩薩のように頭のいい人でなく苦労を重ねた人が仏法を説く人としてふさわしいというのである。知性に基づいた科学技術の世界では知能の高い人が活躍するけれど、心の世界では一流大学卒の人よりも世間で苦労した人の価値が高い。私は長年の経験から自分の周囲を見渡して見て、自分の内外の問題に直接関わって独立して苦労した人の方がカウンセラーとして優れていると感じている。
私自身も河合隼雄先生という優れた指導者について独立していなかったときは、自分の半分は河合隼雄先生に預けていた。だから半分の力で生きていた。だから私の夢の心はお前の人生はその間闇だったと批判した。私は難解なユング心理学を知的に理解してやっていたのだと思う。
幸い河合先生は生きるのに苦労していた人であった。人々は河合先生は面白い本を書人だというけれど、自分が本当に考えていることは本には全く書いていないと中沢新一との対談で述べている。だから、うそつきクラブの会長と自認しているのである。うそつきとは違う。うそつきを自認しているのだから、うそつきではないのである。河合先生は人を正面から見ない人であった。両目をぱっちり開けて正面を向いた写真が一枚もない。河合先生が雑誌世界に投稿された対人恐怖の論文は秀逸である。岩波新書『コンプレックス』に遠藤周作は救われたという。これらを考え合わせると、河合先生は対人恐怖に悩んでおられたと思う。人の顔を正面から見るのが怖かったのではないかと思う。
文化庁長官になるような偉い人にも対人恐怖の悩みがあり、ご自身が優れた心理療法家であるにもかかわらず、生涯その悩みがあったことが人々に深い安らぎを与えているのではないかと私は思う。
頭のいい人の指導は優しくわかりやすいが、肝心のところを外している。心理療法の本は多く読まれるけれど、それによって心理療法がうまくなることはない。
困難を前向きに生きる力、それがカウンセラーの力量であり、それは苦労した人に見習いながら、一人で生き抜く経験によって培われるものである。
6 深層の心にかかわる方法
物語を作るとそこに個人の深層の心が少し出てくるのだが、心理療法ではその深層の心にずっとかかわり続けることが必要である。方法としては、夢、箱庭、遊びが挙げられる。
その方法としては夢が一番良い。夢は昔から神仏の教えを知る方法として重要視されてきた。明恵上人は夢を記録しつづけ生き方を考えてきた。それは常に前向きに「あるべきようは」と疑問形で行き先を考えさせるものであった。
私たちの心理療法でも、夢はこういう「生き方をしてきたのではないか」、「こんなことが度々繰り返されているのではないか」と指し示していることが多い。
夢はこれまでに起こったこと、現在繰り返していること、これから起こるであろうことを比喩的に示していることが多い。夢を見る人は内省する力があり、夢を重視していると自然に人の考えや態度は変わって行く。意図的に変えようとしていなくても変わって行く。
箱庭にも夢のような不思議な力がある。箱庭は意図的に作るけれども、思いつきの遊び半分で作るほど深層の心が出てくる。私が50年前に作った箱庭は今も私の精神生活の姿勢を表していることに驚きを覚える。
子どもの遊びは、思いつきの意識の制御があまり働かない行動だから無意識の心が現れやすい。10歳頃までの子どもはよく遊び、遊びには深層の心がよく現れる。
心理療法の技法では無いけれど、心理査定の対象として、青年期の衝動的な行為は家庭環境の何かを反映していることが多い。青年は衝動にかられて問題を引き起こすことが多く、そこに無意識の心が現れやすい。特に家庭内暴力や家庭外でのいじめや対人関係のトラブルには家庭関係などが反映されていることがある。
7 深層の心の研究
ジェンドリン、Eが『体験過程』でsubtle meaningとらえがたい、名状しがたい、いわく言いがたい意味という言葉をつかって深層の心を表現しようとしたと思っていたが、いわく言いがたい、香水の香りのような希薄な意味ではあまりに表面的すぎる感じで、一般に広く使われる言葉としてはfelt sense感覚的に感じられるものになって、いかにも表面的な意味になってしまった。
深層の心については古来、老子の「道」がもっとも適切な指摘ではなかろうか。老子は難解で、現代の現実には適用できないと多くの人が考えているのではなかろうか。河合隼雄もこのことには全く言及しなかった。私はここに蛮勇をふるって書いておくことにする。深層の心は夢にシリーズから漠然と浮かび上がって来るもので、その漠然としたものが確かなもので、その人の人生を確かに指し示しているからである。
老子第21章には次のように書かれている。
「すべてに入り込む徳(のある人の)立ち居ふるまいは、ただ「道」だけに従っている。「道」というものは実におぼろげで、とらえにくい。とらえにくくおぼろげであるが、その中に象(かたち)がひそむ。おぼろげであり、とらえにくいが、その中に物(実体)がある。影のようで薄暗いが、その中に精(ちから)がある。その精は何よりも純粋で、その中に信(確証)がある。昔からいまにいたるまで、(「道」の)その名がどこかに行ってしまうことはなかった。そして(「道」は)、すべてのものの父たちの前を通りすぎる。どうして私は父たちがそんなふう(に生成するの)だと知るか。これ(直観)によってである。」(小川環樹訳注)(中公新書)
道は恍惚として(おぼろげでとらえにくい)、そのなかにおぼろげでとらえにくいかたちがあって、それも影のようでうすぐらいが、それには力があって、信頼するにたる真があるというのである
夢や箱庭のシリーズのなかに漠然と浮かび上がってくるこころの流れが道と呼べるものではないかと思う。
そのレベルの心を感知する心も漠然としている。
心のなかでささやく小さな声、かすかなほど確かな感覚である。
それは記憶に残りにくい感覚的な意識である。これを金岡秀友は阿羅耶識と言っている(『般若心経』)。
その感覚はもしかしたら、犬や猫と同じ動物的な意識ではないかと思う。瞬間的に感じては消え、記憶に残らない意識である。それは人が動物として感じているものだから、相手や周囲の状況に開かれており、その感覚は確かなものであり、この感覚がカウンセラーの資質としてとても重要であると思う。
7 心理学的な理論の弊害
心は闇であり、コロコロ変わる変転極まりなく、とらえがたい。特に、感情的なもの、愛と攻撃は、一つの衝動の表と裏であり、とらえにくい。また、人に直接かかわりながら心を見ていると、心を見ている主体の自分が相手の心理に影響されるから、心理学的理論による武装が必要だと考え人がある。精神分析の人々は特に人の感情、愛と攻撃に関心を向けているので転移の分析など理論的武装が必要になる。
ある人は心の観察手段として心理学的な理論が必要だと言う。心理学的な理論は心の観測手段だと考えるのである。
また、反対に心を心理学的に見るということは偏見をもっているのだから、もっと素直に偏見なしに見るべきだと主張する。しかし、偏見なしにと言っても、人が見る限り、その人の心はかかわって来るわけだから、偏見なしの観察など出来るはずがない。
そこで河合隼雄は『ユング心理学入門』で、全ての前提を外して素直に見ることはできないから、できるだけ沢山の前提から見ることを主張した。この考えの中にはユング心理学にもとらわれない自由な河合隼雄独自の心理学の可能性が含まれていた。
河合隼雄はユング心理学的にも、精神分析的にも、アドラーの心理学からも、あるいは仏教的な視点やキリスト教的な視点からも、できるだけ多方面から人を見る法が良いと考えた。そのような主張をして30年位経って、河合隼雄は、自分はユングから随分変わってきた、しかし、人々はユングの味付けをしないと読んでくれないから、ユング派としてやっていると語っている。
私は深層心理を考えて、できるだけ先に述べた深層心理の動物的な勘に基づくことを主張したい。動物的な勘は瞬間的で最も頼りないけれども、最も頼りになる、そして誰でも同じく感じているものだから、普遍的だと考える。その動物的な勘を鋭敏にするために内省が常に必要で、内省の手段として教育分析は大切だと考えるようになった。
そういう視点に立って事例報告を見たとき、心理学的な見方の弊害も見えてきた。
ある人が、棺桶が並んでいる夢を見た。人が棺桶のなかの死体を担いでどこかに行った。
その夢から、ユング派のカウンセラーは死と再生を考え、その人の死んだ部分がいずれ再生してくると考えた。
ユングは人の死の夢を見た。しかし、フロイトは自分の死をユングが願っていると解釈されては困ると思って、その夢をフロイトに言わなかった。夢は願望充足であるというフロイトの図式が心の関係を邪魔したのである。
拒食症のあるものは「聖なる拒食」、つまり、殉教だと考える人もある。拒食症は中々治らないし、静に死に至る自殺行為だから、それを聖なる拒食、殉教と考える人もある。けれども、動物的なレベルからは考えられないことである。動物に自殺はない。しかし、人間は宗教システムにかかわると殉教を考え、殉教としての拒食があり得ると考えるのである。
このように人の宗教も含めた心理学や政治や社会のシステムが人の心の見方を阻害してしまう可能性があることを知って置かねばならない。
このように考えると、机に向かって心理療法はこうあるべきだと考える人の著書が心理療法に最もためにならないということになるかもしれない。皮肉なことである。実際物書きの先生の下からは物書きの弟子が育ちやすく、心理療法の実際家は育ちにくい。
8 真相心理療法の実際
以上述べたようなことを考えて心理療法をするとどうなるか。
心理療法では、クライアントの心に思い浮かんで来ることをできるだけありのままに話しさせて、それを聞いてカウンセラーとして感じたことをできるだけ隠さず率直に述べ、本当の話合いをしていくことが真相心理療法につながっていくと思う。
クライアントの話をありのままに聞く上で共感と受容は当然のことだが、言葉の裏にある感情の受容でとどまることはしない。例えば、この人は母親の娘として尽くそうと考えながら、一方で、母親の言葉に傷ついている。傷つきながらも母親から離れられない。それはどうしてだとさらに考えながらさらに話を聞く。その先にまだわかないことが深層に残っているはずだ。これを何とか明らかにするために夢や箱庭を使う。
夢だと丁度タイミングを見計らってヒントを与えてくれる。時はな昔行為ことがあったと教えてくれて、それで安心することがある。
本当のことがわかると人は安心する。安心すると生きる意欲が湧いてくる。
すべてはこのように本当のことを明らかにしていくことで済む。
人はほんとうのことがわかると安心する。これが大原則である。
人はいろいろなことを経験して成長してくる。どんなに間違ったことでも嫌なことでも、過去に起こったことは取り消すことができない。経験したことは消えない。
しかし、一度経験したことは一つ円い岩を自分のものにしたようなことで、それは自分の心の家の土台になる。その経験をしっかり見つめたほど硬い岩になり、心の家の基礎として役に立つものである。教育分析は心の家を自分の経験という土台に基礎づけることである。良い経験だけでなく悪い嫌な経験もすべて役に立つことが意味深いと思う。
中国の西遊記、孫悟空の話は、妖怪退治の話で、漫画になり、多くの人は面白く読んでいる。この妖怪退治の話は、日本も桃太郎の話とは少々訳が違う。桃太郎は鬼を退治して宝物を持って帰るが、孫悟空は妖怪を退治してやって謝礼をもらうわけではない。西天に取経に行く和尚の道の障害を除く役割を孫悟空は担っている。人生の目的に向かって生きる者を他受けるために妖怪退治をする。つまり、コンプレックスを取り除く仕事をしているのである。これはまさしく心理療法の作業ではないか。心理療法の本として『西遊記』を読むとどうなるか。
孫悟空は妖怪退治をする。その際、妖怪の本性がわかると妖怪退治が出来るである。妖怪を退治するためには妖怪の本性を知らねばならない。妖怪を菩薩が取り押さえたときでも、悟空は菩薩に妖怪の本性は何ですかと尋ねている。孫悟空にとっては妖怪を退治するだけでなく、妖怪の本性を明らかにすることも大切な作業なのである。
これは私の真相心理療法の考え方と一致する。
孫悟空は猿であり、動物的な勘をもって、自由自在に生きる存在で、ここに治療者の資質が示されている。