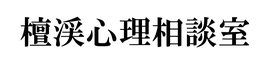コンプレックスという考え方はユング心理学から出てきた。それは普遍性を持って精神分析の世界で広く使われるようになった。母親コンプレックス、父親コンプレックス、劣等感コンプレックス、女性コンプレックス、男性コンプレックス、などなどきりがない。
コンプレックスのイメージはたとえて言えばもつれた糸のかたまりのようなものである。うまく解けば有用になるが、うまく解けないと心のわだかまりとしていつまでも心の中に残る。それは糸屑のように捨てることはできず、心の中で気になる嫌なものの代表である。
このコンプレックスを克服しようとして努力するとき偉大なものになる可能性がある。宮沢賢治の『セロ弾きのゴーシュ』はそのテーマのお話である。
音程も不確かでいつも間違えてばかりいるセロ弾きのゴーシュは楽長から叱られるので、毎晩一所懸命に練習する。すると猫やカッコウがやってきてもっと弾いてくれというので、ゴーシュはやけくそになって弾く。そしてネズミの親子がやってきてお母さんがセロを弾いてこの子の病気を治してくださいという。何故かと聞くと、これまで来た猫やフクロウの親はゴーシュのセロの演奏を聴いて病気が良くなったからだという。何故かわからないけれどゴーシュは子ネズミをセロの中に入れて弾くと子ネズミは元気になる。そういうことがあって本番の演奏会は成功し盛大な拍手を受ける。アンコールは用意していないのでゴーシュがアンコールの演奏をするように舞台に押し出されてしまう。ゴーシュは猫を狂わせた虎刈りの曲を弾いて大喝采を浴び、楽長にもやればできるではないかと誉められた。
セロ弾きのゴーシュは劣等感の塊であったろう。この劣等感を克服するために懸命に努力をしたら、猫やとりやネズミが出て来てゴーシュの成長を助けてくれたというのである。
このように劣等感を克服しようとして努力すると、その努力によって普通以上の存在に飛躍することができる。最近有名になった『英国王のスピーチ』で紹介された吃音の人のスピーチの素晴らしさはその良い例である。また、日本映画監督新藤兼人さんはかなりの母親コンプレックスであろう。しかしその母親へのこだわりによって偉大な映画が生まれたのではないかと思う。コンプレックスは生きる力となる。
何々コンプレックスというものを持っていない者はどうなるのか。ただ、生きるのが下手、苦手、生きづらいというのもある。何事もあまりうまくいかない。どこから手を付けて良いかわからいというのもある。生きること自体がコンプレックスなのだ。
こういう人は、とにかく心の深淵、何もない深淵を見ないと仕方がない。
ところが心の深淵には本当に何もない、どんな偉い坊さんでも心の中を見たら何もない。禅のお坊さんが大変な努力をして到達するところは心の中の何もないところである。大円境地というのがそれである。
多くの閉じこもりの青年が何をしたらよいかわからないという。自分の心の中を見て、何もないからそう言うのである。閉じこもりの青年は初めから大円境地に近いのかもしれないが、何せ、この何もない無の大円境地に向き合うにはすごい自我の力を必要とする。自我の力が弱いまま心に向き合うと、いつまでも何をしてよいかわからず、ぐずぐずと時を過ごしてしまうだろう。セロ弾きのゴーシュのように下手くそでもいい、人中に入ってやって楽長に叱られるという経験をすべきではないか。
セロ弾きのゴーシュは下手くそだから寝るのも忘れて無心に練習する。すると真夜中にいろいろな動物に出会う。やってきた動物は容赦なくゴーシュに注文をつける。その結果とんでもないことになる。しかし、そのことが病を癒すような生きた演奏につながった。その時ゴーシュが猫やカッコウに対してとった態度は常識から見てまともではないが、その心理がよりよく生きることにつながっていることに注目したい。
賢治は、心の中で劣等感のかたまりのゴーシュを生きて、物語を展開し、劣等感を生きることのどれだけすさまじいことかを内的な真実として私たちに示した。それは賢治という人間の内的真実だから心に響いてくるのであろう。
生きる力を得るには、何々コンプレックスというものはなくても、とにかく生きたいと思って心の深淵に触れるようなことをし続けていくことが大切なのではないか。物語『セロ弾きのゴーシュ』はそういうことを私に教えてくれた。